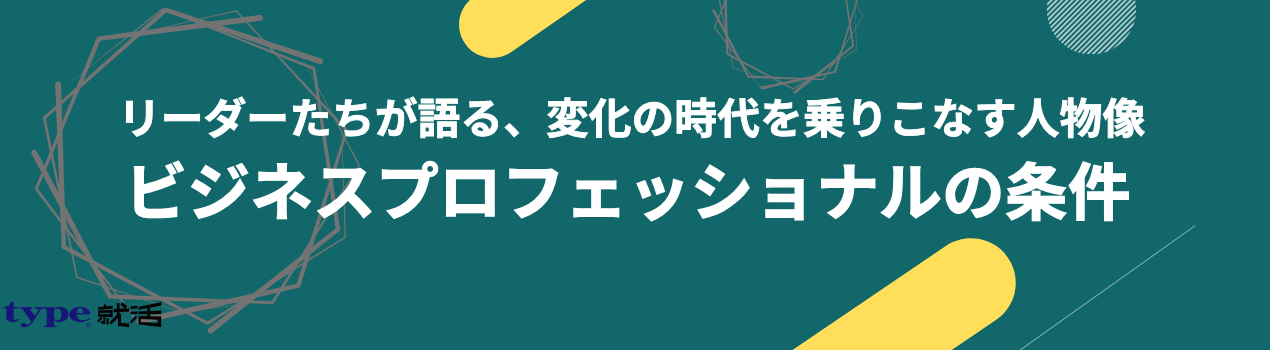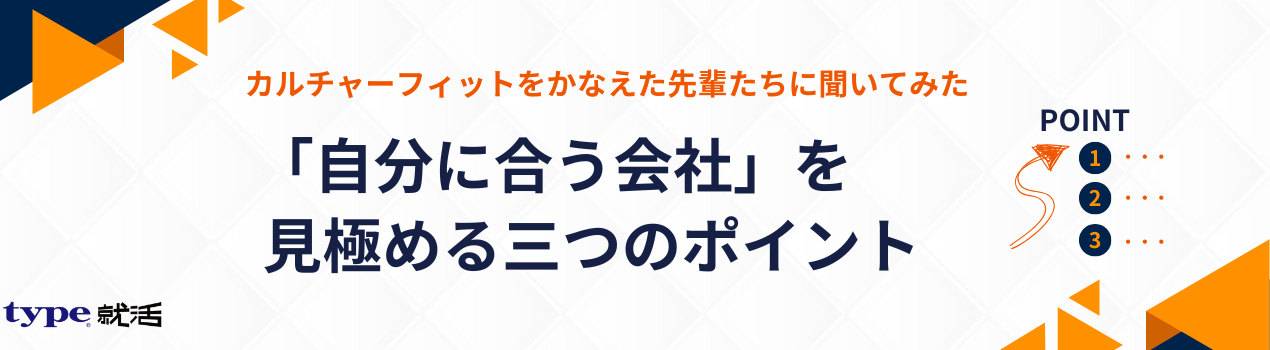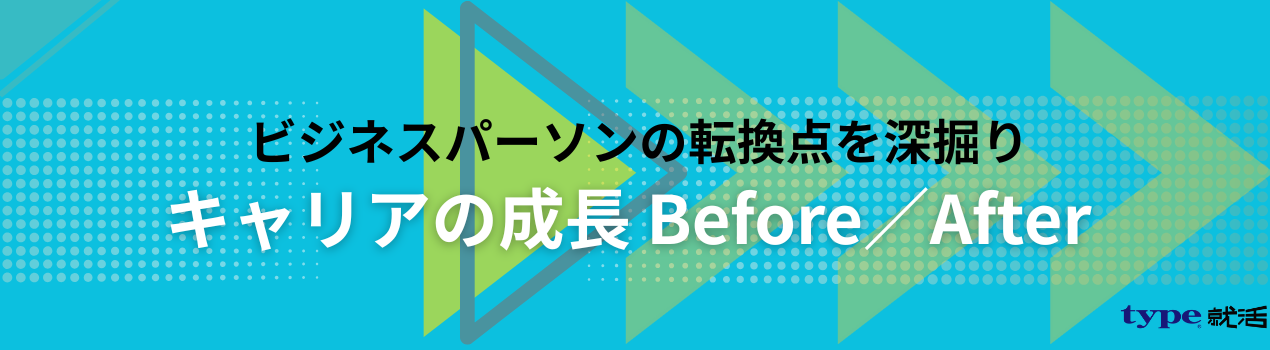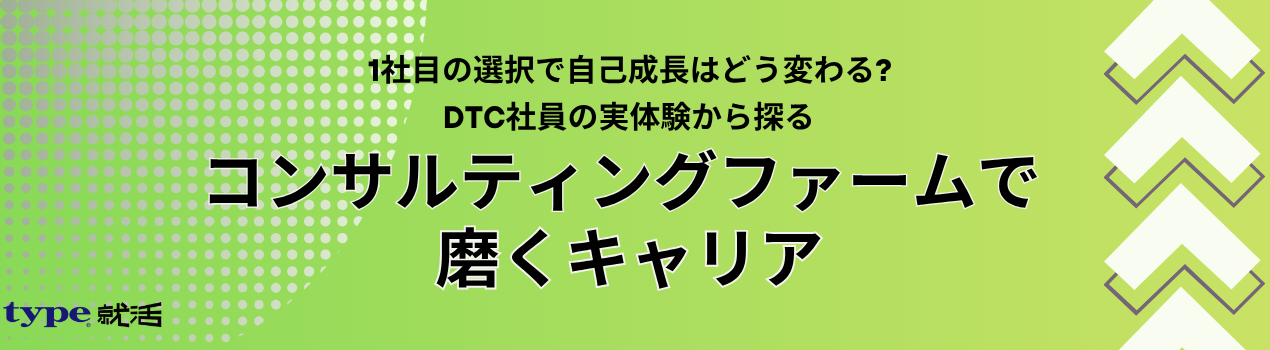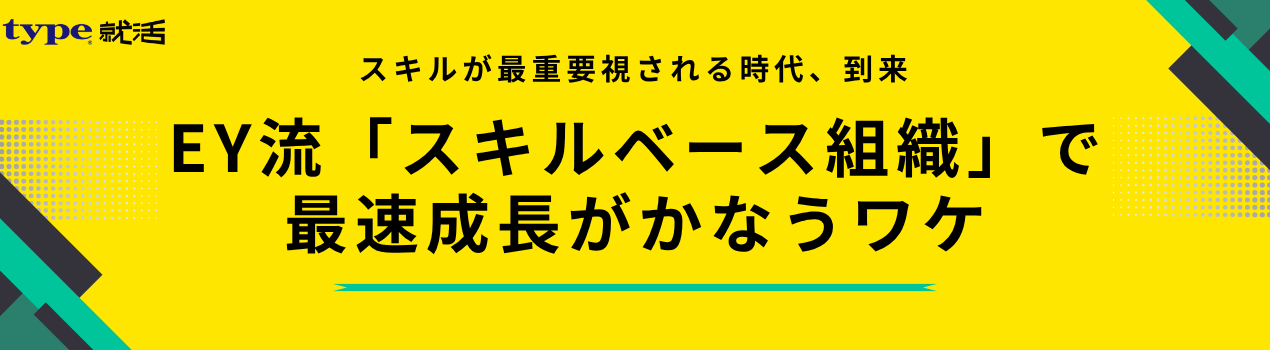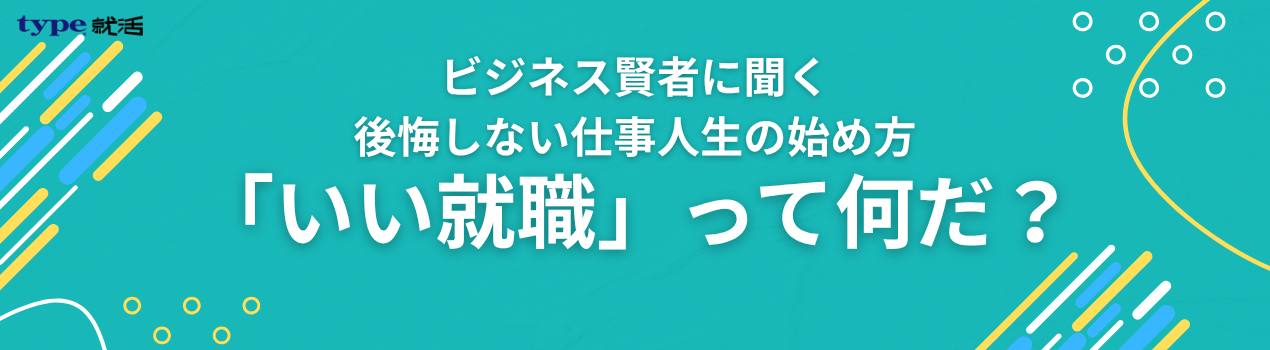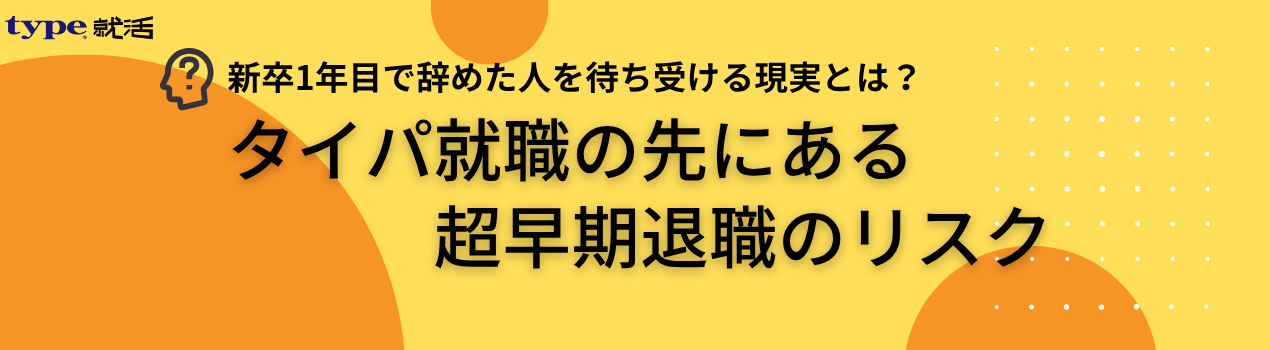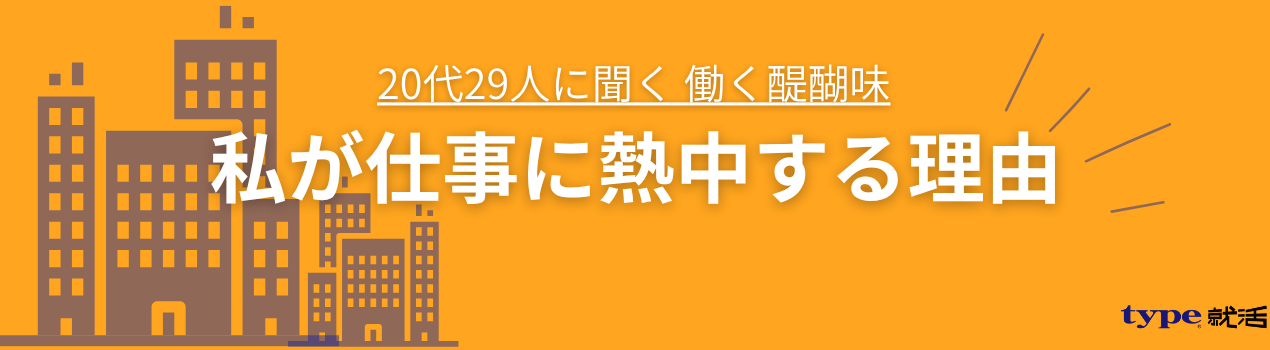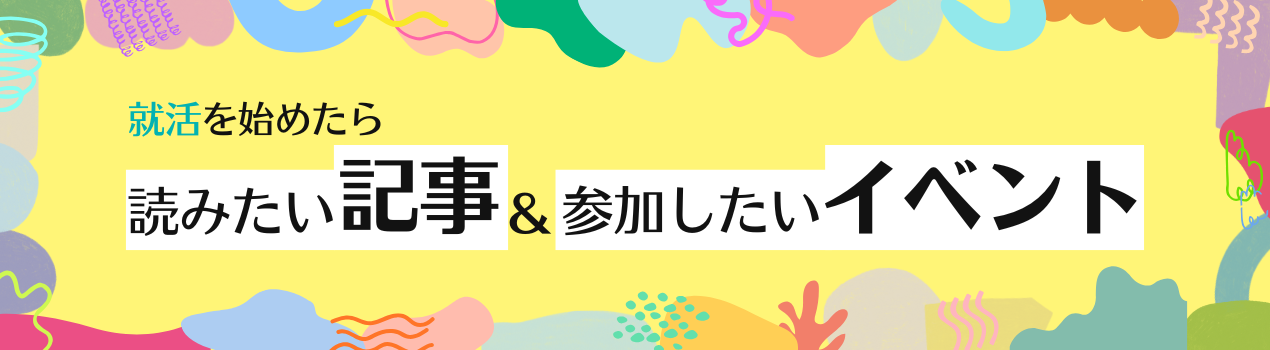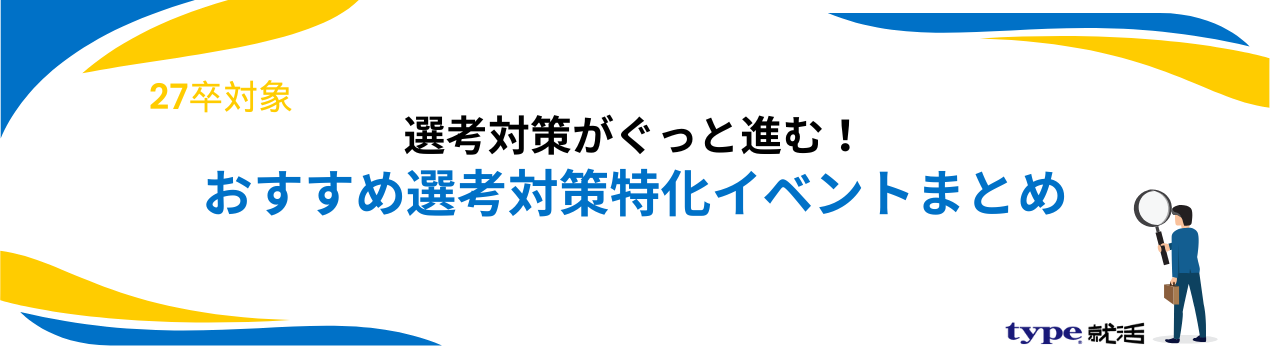記事一覧
381件中111~120件を表示
検索
Search
-
ストレスが溜まったとき、どのように対処しますか? ー 回答の難しさとコツ
- 26卒
- 27卒
- インターン
- キャリア
- コラム
- 初心者向け
- 就活
- 就職活動
- 面接
- 面接対策

-
【就活体験談】外資大手Webサービス企業内定者/コンシューマー総合職
- 2026卒向け
- type就活インターン生
- コラム
- スケジュール
- 内定者
- 初心者向け
- 就職活動
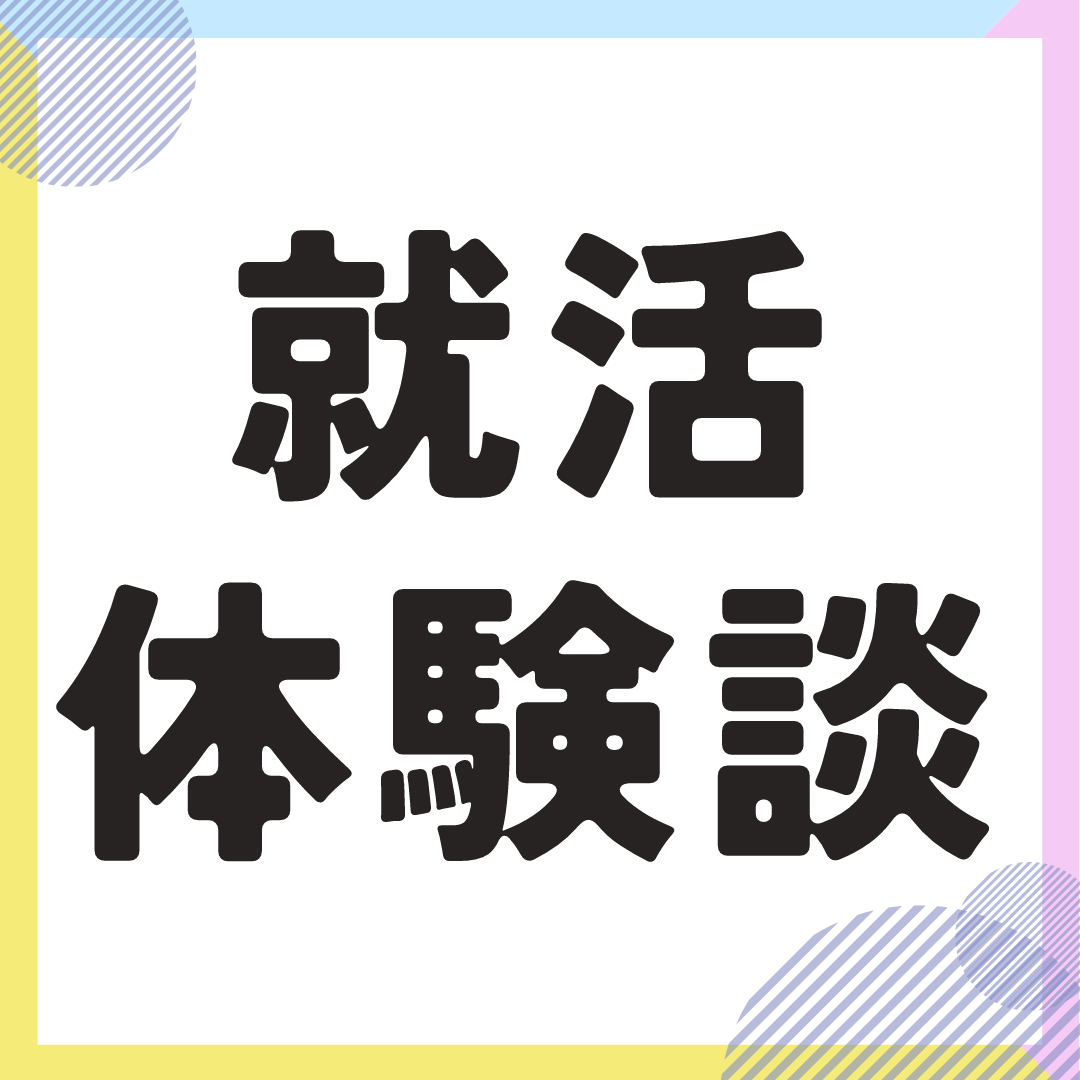
-
【就活体験談】日系大手コンサルティングファーム内定者/コンサルタント職・ビジネスプロデューサー職
- 2026卒向け
- type就活インターン生
- コラム
- スケジュール
- 内定者
- 初心者向け
- 就職活動
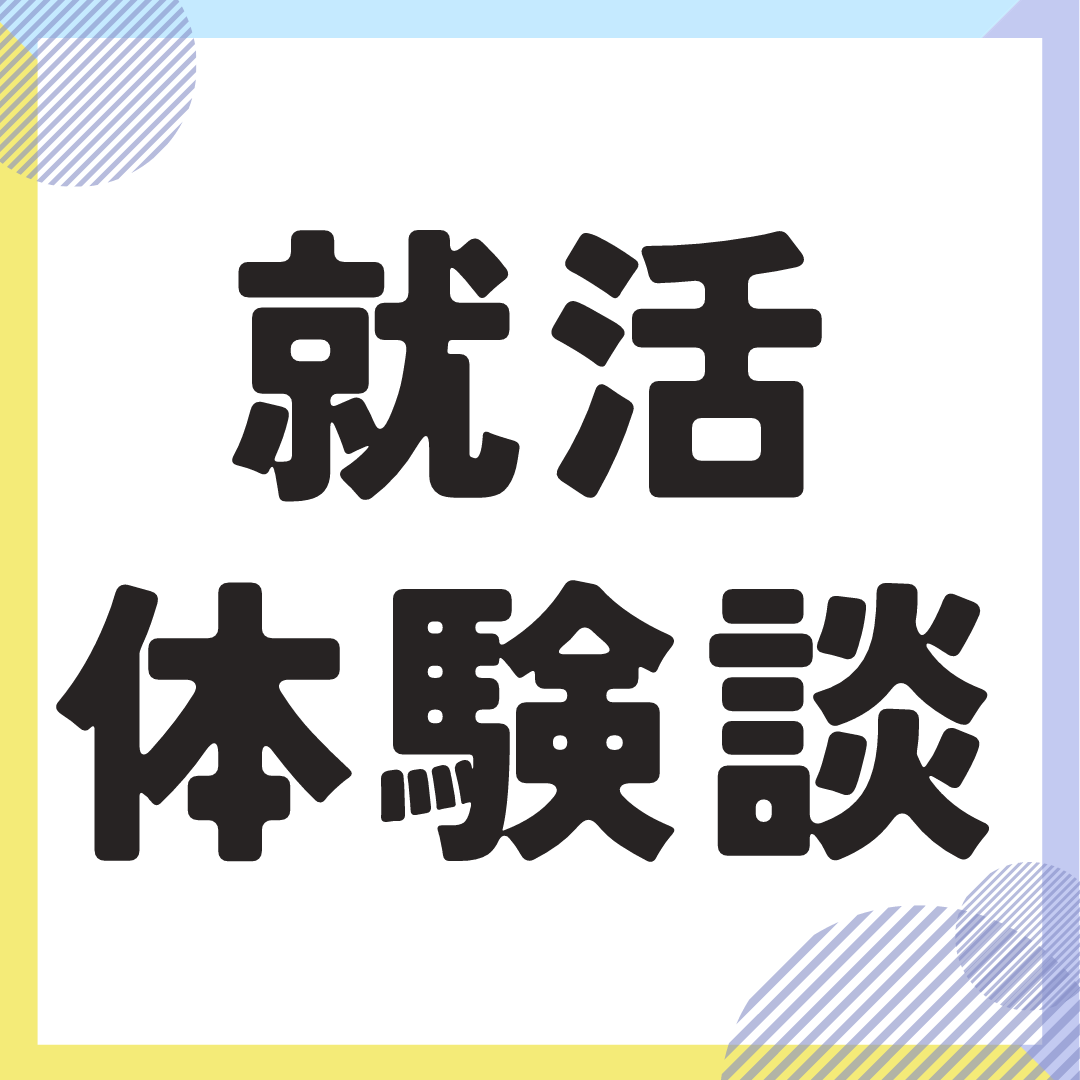
-
【就活体験談】日系大手IT企業内定者/ ビジネス職
- 2026卒
- 2027卒
- 26卒
- 27卒
- type就活インターン生
- コラム
- スケジュール
- 内定者
- 初心者向け
- 就職活動
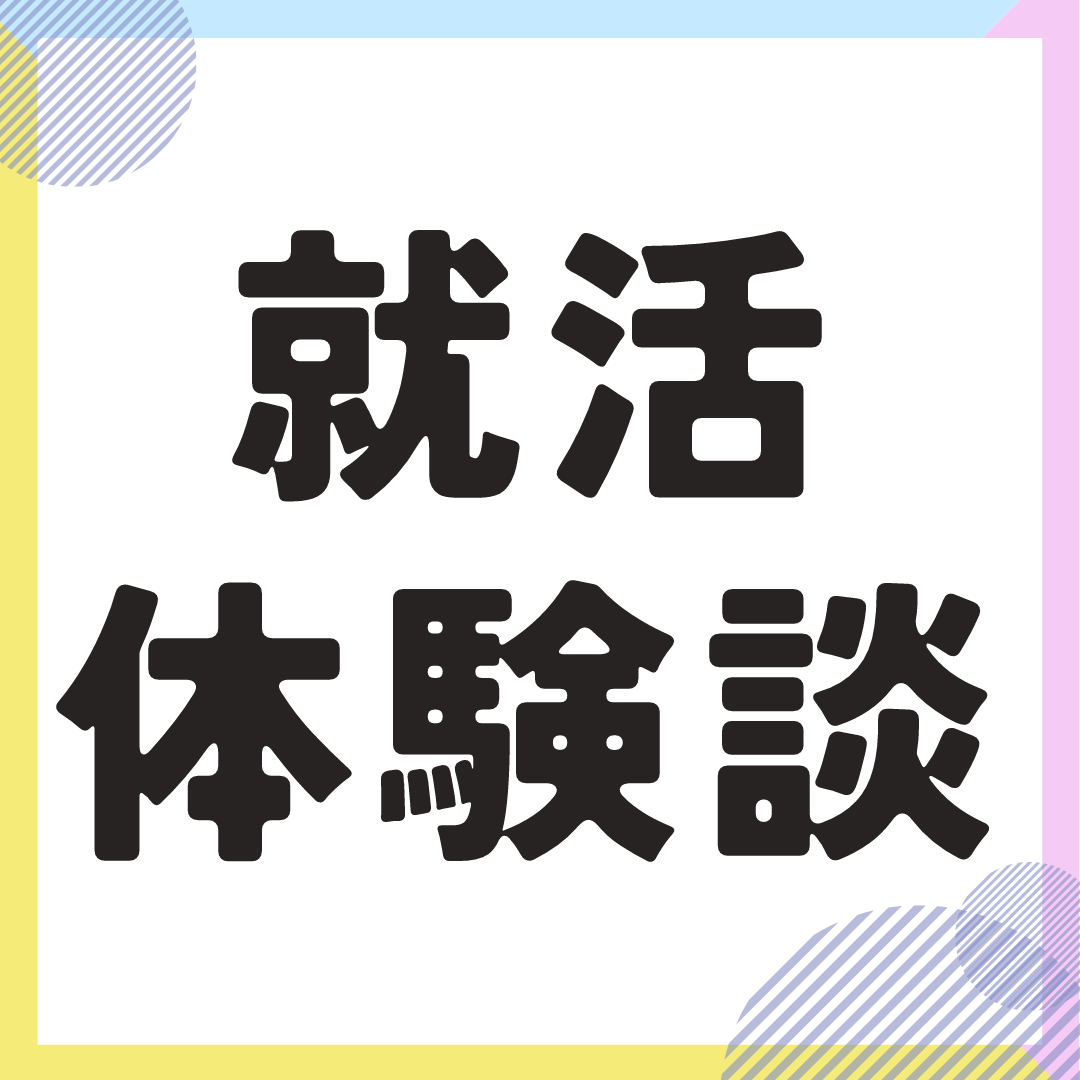
-
今後のキャリアプランを教えてください ー 回答の難しさとコツ
- 26卒
- インターン
- キャリア
- コラム
- 初心者向け
- 就活
- 就職活動
- 面接
- 面接対策

-
【就活体験談】日系大手人材業界内定者/ 総合職
- 2026卒
- 26卒
- type就活インターン生
- コラム
- スケジュール
- 内定者
- 初心者向け
- 就職活動
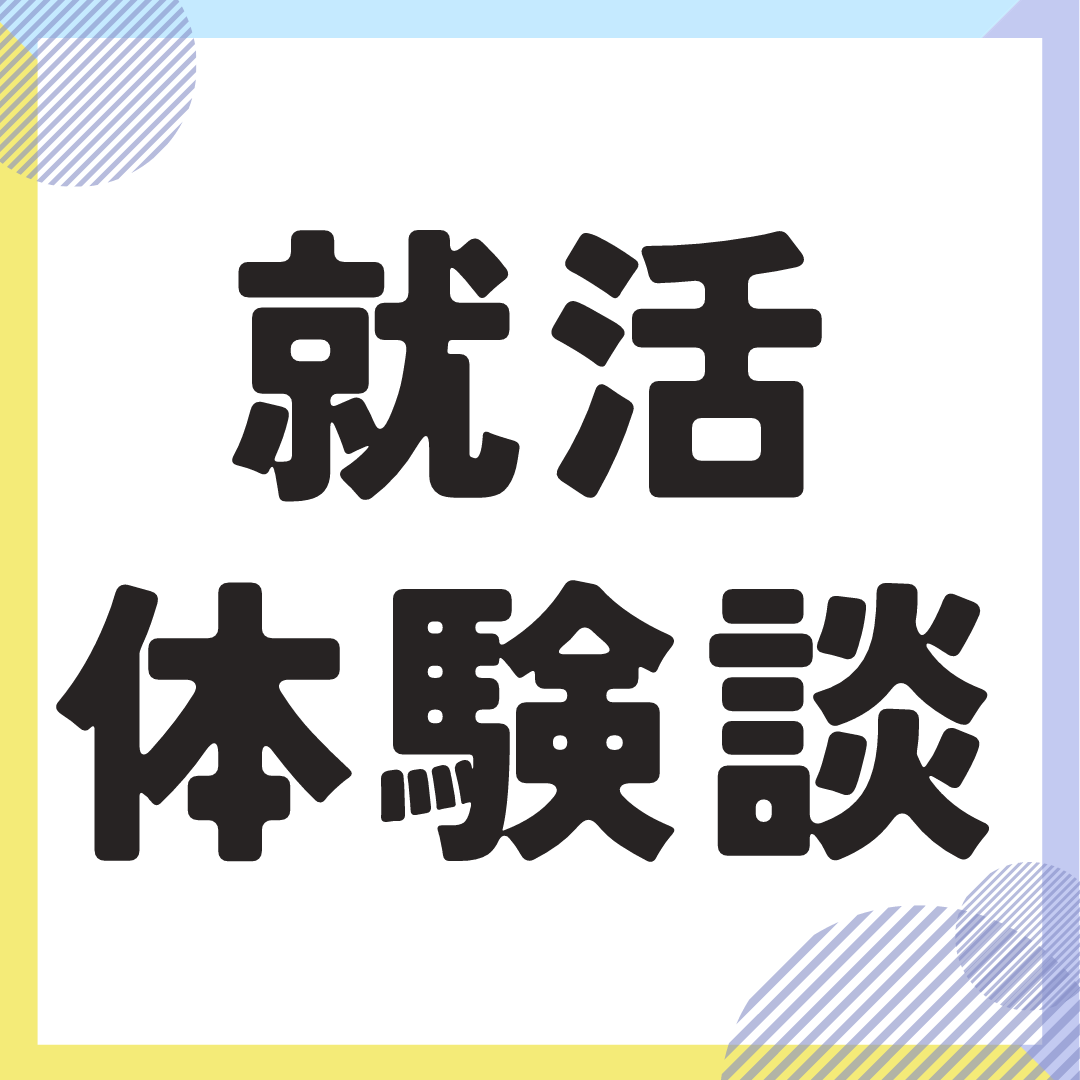
-
あなたの強みと弱みを教えてください ー 回答の難しさとコツ
- 26卒
- インターン
- キャリア
- コラム
- 初心者向け
- 就活
- 就職活動
- 面接
- 面接対策

-
【就活体験談】日系大手メーカー内定者/ 設計エンジニア
- 2026卒
- type就活インターン生
- コラム
- スケジュール
- 内定者
- 初心者向け
- 就職活動
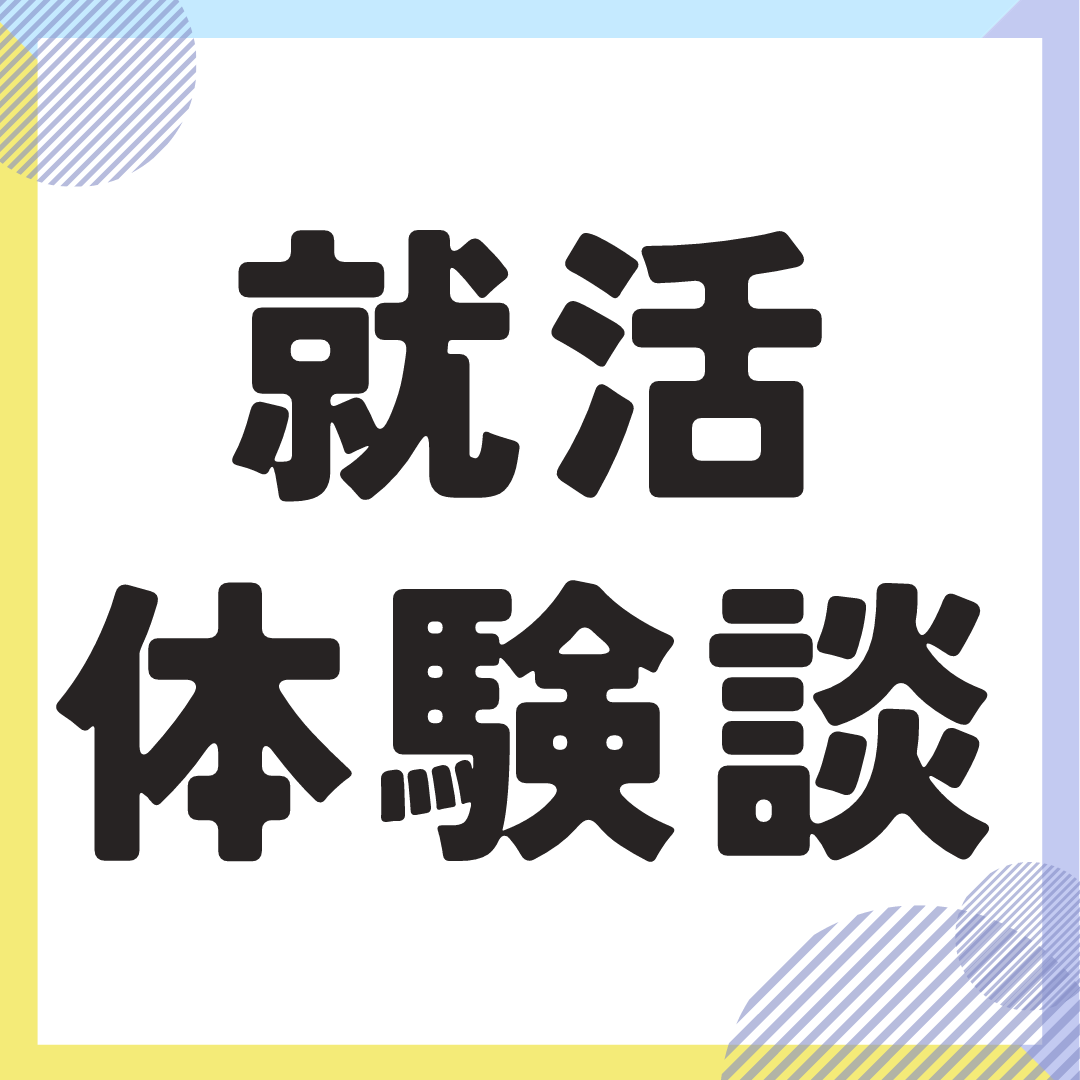
-
学生時代に力を入れたことは何ですか? ー 回答の難しさとコツ
- 26卒
- インターン
- キャリア
- コラム
- 初心者向け
- 就活
- 就職活動
- 面接
- 面接対策

-
面接で話す内容以外で注意すること
- 26卒
- インターン
- キャリア
- コラム
- 初心者向け
- 就活
- 就職活動
- 面接
- 面接対策

381件中111~120件を表示