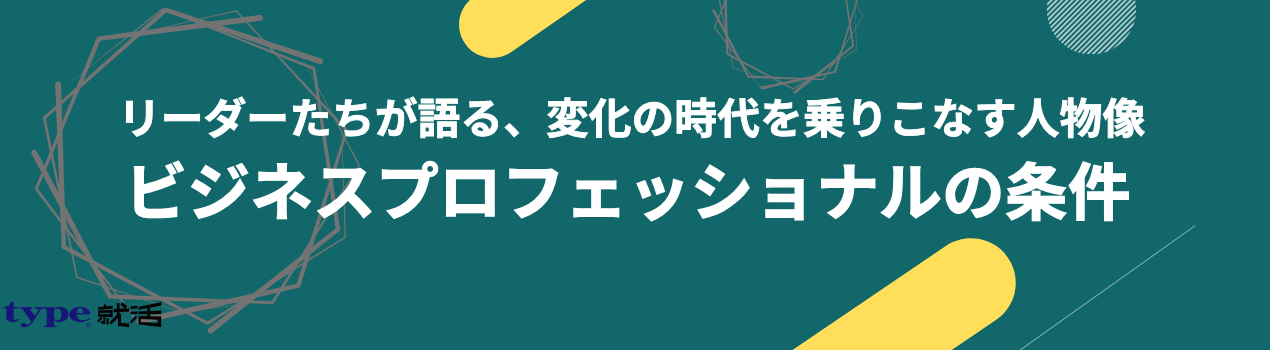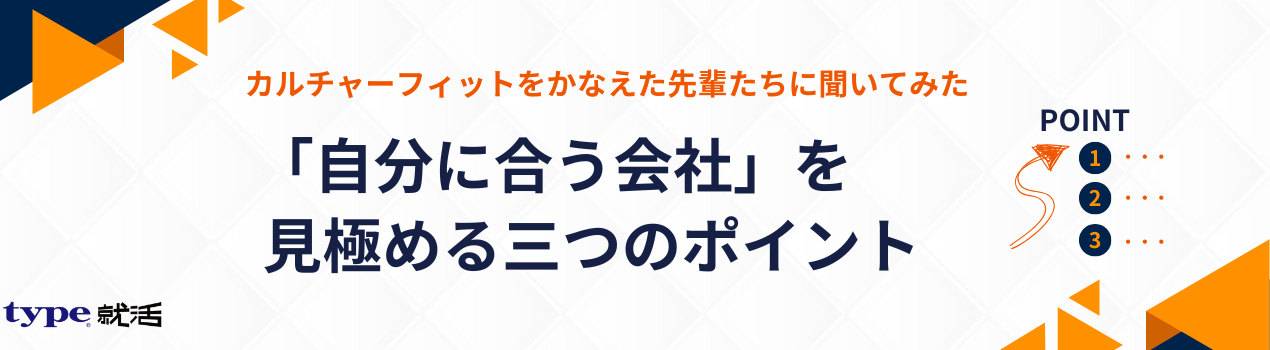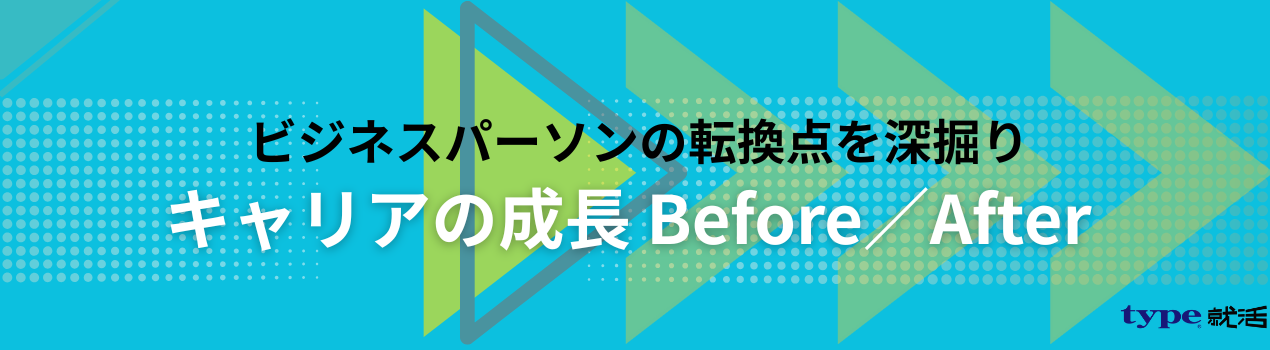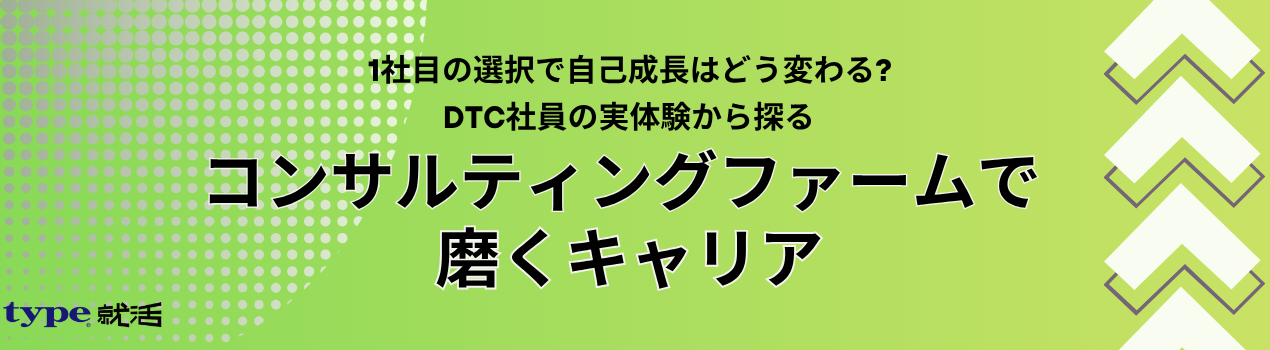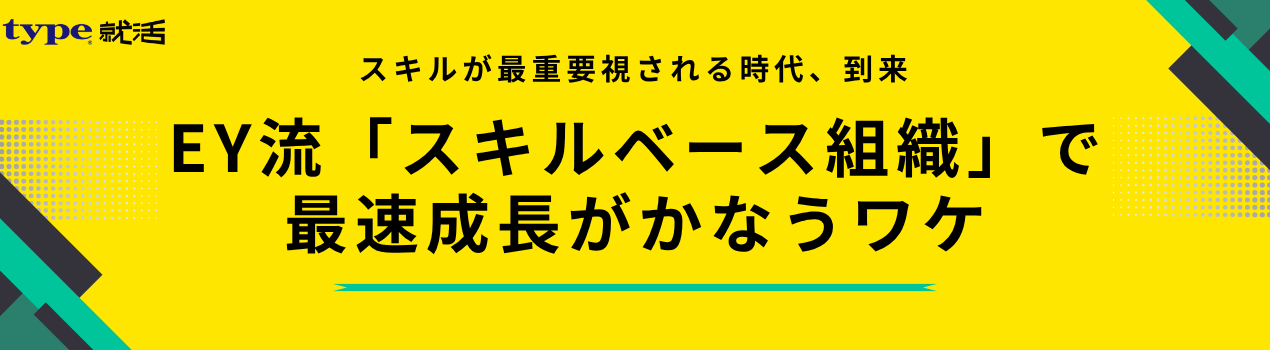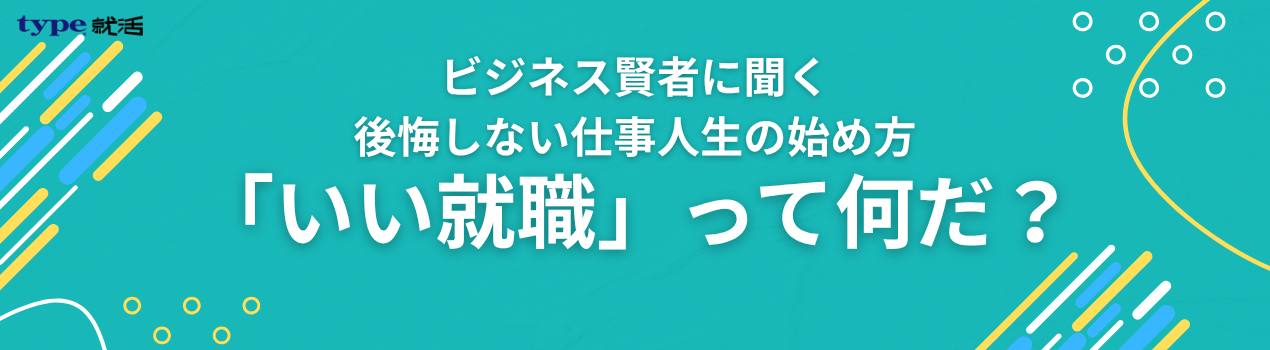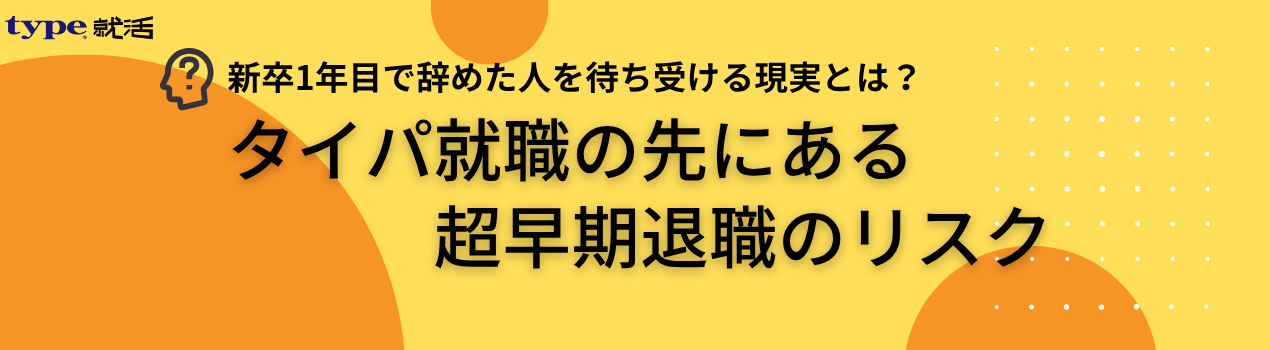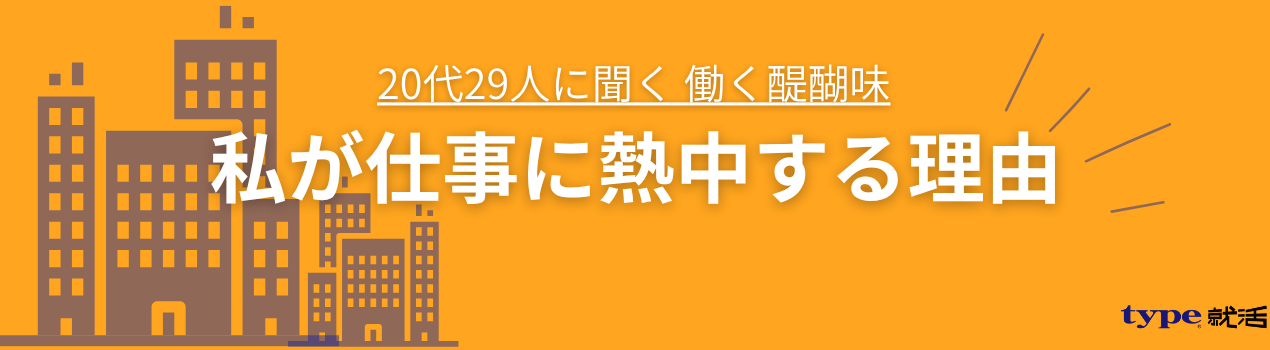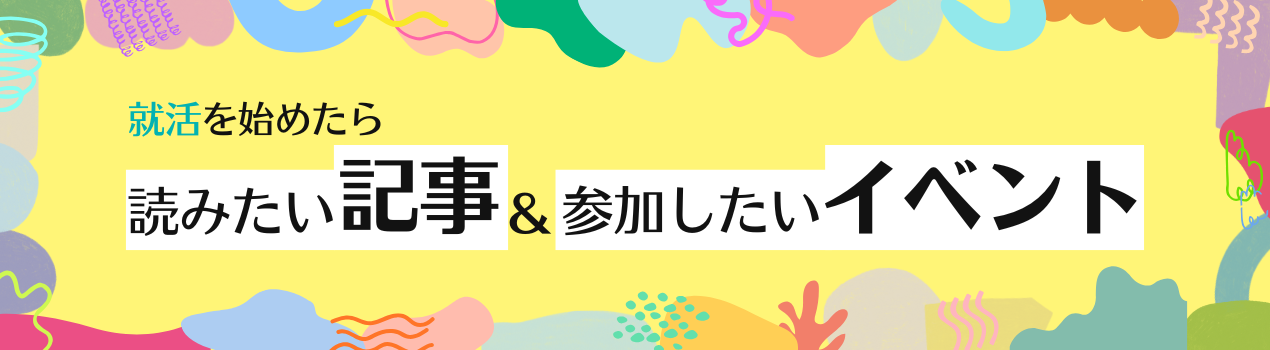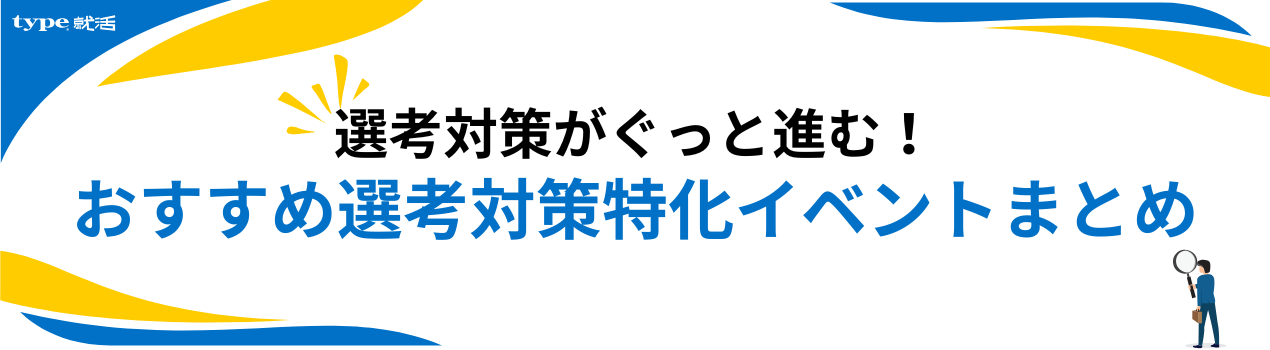記事一覧
38件中1~10件を表示
検索
Search
-
【28卒向け】総合商社業界を徹底解剖!ビジネスモデル、主要5社の違い、就職活動のポイントまで
- 2028卒
- 28卒
- 29卒
- インターン
- コラム
- 就活
- 業界研究
- 総合商社

-
【28卒】IT業界研究を徹底解説!IT業界の仕組み・分類について
- 2026卒
- IT業界
- type就活インターン生
- インターン
- コラム
- 業界研究

-
すぐできる!業界研究のやり方・徹底解説|就活<28卒>
- 28卒
- 29卒
- コラム
- 初心者向け
- 就職活動
- 業界研究

-
メーカーとは?業界の仕組み・仕事内容・種類をわかりやすく解説【28卒/就活】
- 28卒
- 29卒
- メーカー
- 就活
- 業界研究
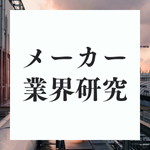
-
【28卒|徹底解説】金融業界とは?金融業界の仕組み・業務内容がわかる!(業界研究)
- 2028卒
- type就活インターン生
- インターン
- コラム
- 外資金融
- 業界研究
- 金融

-
【28卒】デベロッパーとは?就活生に人気の理由と不動産業界の仕組みから徹底解説!
- 2027卒
- 27卒
- type就活インターン生
- インターン
- コラム
- デベロッパー業界
- 就職活動
- 業界研究

-
【28卒向け】NTTデータ、富士通、NEC、ソフトバンク…IT大手4社の違いを比較解説|事業内容・社風から選考対策まで
- 28卒
- 29卒
- IT業界
- インターン
- 企業研究
- 初心者向け
- 就職活動
- 業界研究
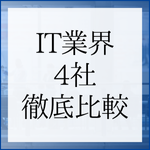
-
【28卒向け】デベロッパー志望なら必読!主要5社(三菱地所・三井不動産・住友不動産・東京建物・東急不動産)の特徴と選考フロー徹底比較
- 28卒
- 29卒
- インターン
- デベロッパー
- デベロッパー比較
- 企業研究
- 初心者向け
- 就職活動
- 業界研究
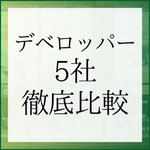
-
コンサル大手5社の違いは?マッキンゼー・BCG・ベイン・アクセンチュア・NRIの強みと選考フローを比較【28卒向け】
- 2028卒
- 28卒
- インターン
- コンサル
- コンサル 比較
- 企業研究
- 初心者向け
- 就職活動
- 業界研究
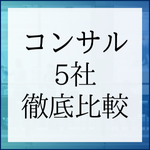
-
【27卒向け】電通・博報堂・サイバーエージェント・ADK、広告大手4社の違いを比較解説|事業内容・社風から選考対策まで
- 27卒
- 28卒
- インターン
- 企業研究
- 初心者向け
- 就職活動
- 広告業界
- 業界研究
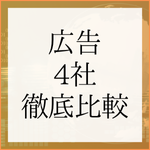
38件中1~10件を表示