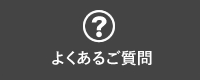-
- 記事
- 業界研究
- コンサル
- 合同会社デロイト トーマツ/コンサルティング
- DTCが見据える コンサル新時代
2019/12/1 更新 合同会社デロイト トーマツ/コンサルティング
DTCが見据える コンサル新時代
- デロイト トーマツ コンサルティング
- AI
- コンサルティング
- テクノロジー
- ビジネス
- 企業理解
変革期を生き抜く“次世代”に求められることとは?
DTCが見据えるコンサル新時代ここ数年、技術の進歩や世界情勢の変化に後押しされ、世の中のあらゆる領域で “大変革期”が叫ばれている。コンサルティングファームにおいても、ビジネスモデルや、コンサルタントのキャリア形成の在り方が大きく変化していくことが予想されており、「今まさにコンサル新時代が訪れようとしている」とデロイト トーマツ コンサルティング代表執行役社長の佐瀬真人氏は語る。では、そんな激動の時代に、次世代コンサルタントにはどんな成長が求められているのか?佐瀬氏および同社人事、現場社員へのインタビューから「新時代のコンサルタント像」を探る。
不確実性が増す世の中で、 ゼロからビジネスを創る力を育む

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
代表執行役社長
佐瀬真人氏
2000年4月にDTCに新卒入社。自動車業界を中心にコンサルタントとしてキャリアを積み、近年はデロイト アジアパシフィックやデロイト トーマツ グループのセクターリーダーを歴任。19年6月より現職
デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)に限らず、今コンサルティング業界は大きく変わろうとしており、まさに「新時代」が訪れようとしています。中でもインパクトがあるのは、グローバル化とテクノロジーの進化によるクライアントニーズの変化です。
ここ数年、グローバル化に関するクライアントニーズは欧米や中国へのマーケット拡大が優先されていました。しかし、それらの市場の成長が徐々に鈍化してきたことにより、その他のマーケットを含めた海外戦略のポートフォリオをつくることが求められるようになったのです。
日本企業がグローバル進出をする上で、マーケティングの手法や組織づくりなどは、単純に横展開していけばいいというものではありませんから、コンサルティングファームにはより一層幅広い知識と対応力が求められるようになりました。
またテクノロジー分野では、5Gをはじめとする新たな技術がどんどん生まれてくる一方で、陳腐化も早く、取り残されないための企業戦略や研究開発が急務となります。そして、それらを活用するコンサルタントの知識も常にアップデートすることが求められるようになったのです。
このような外部環境の変化を受けて、これからのコンサルティングファームには何が求められるのか。われわれはもはや「正しい戦略づくり」だけでは足りないと考えています。今までのコンサルティングファームは、事業を構想することでクライアントに価値を提供していましたが、これだけ変化の激しい時代、不確実性の中で構想しただけの成果物では意味を成しません。
その際に、DTCがこれからもクライアントの真のパートナーとして選ばれる理由は二つあると考えています。一つはDTCのコンサルタントはプロフェッショナルとしてあらゆる事業領域を網羅しており、世界各国のデロイト トーマツ グループが有する監査・税務・法務・コンサルティング・ファイナンシャルアドバイザリーなどの強みを生かしてグローバル規模の案件をカバーできること。
さらにもう一つは、課題解決のスピード力です。クライアントが実現したいビジネスの検証と実行を、社内のリソースを使ってスピーディーに実践していけます。 例えば数年前であれば、1年かけてビジネスの計画や企画を精査し、次の1年で試験的にプロジェクトを実施。足かけ2年で、やっとサービスリリースが確定する、といったスピード感が一般的でした。しかし外部環境の変化が激しい今の時代は、ビジネスを3カ月で企画し3カ月で実証、と計6カ月でリリースするようなスピード感が求められています。
なぜDTCが他社に比べて、広範囲な領域でスピーディーなコンサルティングを手掛けられるかというと、DTCのコンサルタントは新卒の時から、複数の業種・業態のコンサルティング案件にアサインされ、幅広い領域をカバーできるスキルを身に付けているから。現在2700名を超える社員それぞれが、幅広い領域でプロフェッショナルといえるコンサルタントであることに加え、グループの総合力と国際力を生かせるDTCだからこそ、これからのクライアントニーズにもスピーディーに応えていけると確信しています。
経験値や制約にとらわれない 若手ならではの発想が重要
先述したクライアントニーズの変化を受けて、若手コンサルタントが担当する仕事内容も変わっていくと思います。なぜなら、あらゆる産業で変革が求められている昨今、若手コンサルタントを中心にゼロスタートのビジネスを立ち上げる機会が増えているからです。新規ビジネスを立ち上げる機会が増えることによって、DTCでは若手のうちから、「ゼロから無限大の可能性をつくる」という醍醐味を体験でき、経営者視点を持ちながらビジネスを展開していくことができます。
それらの経験が、自分自身でビジネスを運用するアントレプレナーシップ(企業家精神)を醸成します。するとコンサルタント自身のキャリアやスキルに厚みが出るだけではなく、より一層高い視座を持ったビジネスパーソンへと成長することにつながるのです。
今までであれば、コンサルタントには担当する領域に関する知識など、ある程度の経験値を要するスキルが求められていました。しかしこれからは、答えのない問題を解く力や、過去の成功体験や業界の制約などに縛られないフレッシュで柔軟な発想力が求められるようになると思います。もちろん、従来と変わらず「自分はこの分野のプロフェッショナルである」といった得意領域を持つことも重要ですが、これからどうなっていくのか、未来のことが予想しづらくなってきた世の中では、データや経験値の範囲に収まらない提案こそがコンサルタントには必須になってくるはず。だからこそ、われわれはこれから入社する若手社員に一層の期待を持っているのです。

「日系」「外資系」企業の “良いとこ取り”ができる
DTCでは近年、若手のうちからビジネスの現場をリードするコンサルタントを育成するために、新人の研修により一層力を入れています。中でも特徴的なのは、新卒入社直後に実施される約2カ月間の『BA(ビジネス・アナリスト) ブートキャンプ』と呼ばれる研修です。プロジェクトに配属されてすぐに役立つスキルセットのトレーニングや、チームワークを学ぶためのプログラムを用意しています。その中でもユニークなのは、研修の中で合宿や運動会などを実施すること。
コンサルタントは一匹狼のように仕事をすると思われがちですが、その仕事の本質は「チームワーク」です。他者を気遣い、切磋琢磨することの重要性を実践的に学びます。 基礎研修を終えた後、新人はプールと呼ばれる組織に所属し、複数のプロジェクトにアサインされます。複数の業種・業態のコンサルティングに携わることで、早い段階で自分の強みを見つけたり、自分が価値を出せる分野は何なのかを考えたりすることができるのです。また、必ず先輩社員がそばに付いて並走してくれることで、先述した新人らしいフレッシュで柔軟な提案を行いやすくなるでしょう。
このように、DTCには会社の同僚や上司との距離が近く手厚い研修がある日系企業的な側面と、実力主義で幅広い仕事を任せていくという外資系企業的な側面があります。そういった社風の中で、自分の専門領域を探しながら、アントレプレナーシップを育んでいくというのは、ファーストキャリアとして非常に有効だと、私は思います。
若手のうちからビジネスの現場に飛び込み、実践で使えるスキルを伸ばしながら「骨太なコンサルタント」になりたい人にとって、今のDTCほど良い環境は他にないでしょう。これから入社を考えている人には、DTCで「新時代のコンサルタント」として成長してくれることを期待しています。
「次世代コンサルタント」に求められる3つの力とは?
1.答えのない問題を柔軟に解く力

顧客に貢献できるビジネスは数多くありますが、お互いの利益が一致するビジネスはそう多くありません。自分自身の努力がお客様のためになる。また、顧客利益を追求し続けることが仕事の成果につながるという点は、まさに私が求めていた、本当の意味で顧客に貢献することができる仕事でした
2.制約にとらわれないフレッシュな発想

過去の成功体験や業界の制約などにとらわれていては、斬新な課題解決策は生まれてこない。若手ならではのフレッシュな発想や、「当たり前を疑う」能力は、時にプロジェクトに大きなブレイクスルーを生み出す
3.「自分ならでは」と言える専門的なスキル・能力

クライアントニーズの難易度がより一層高まる今、平凡な提案には価値がない。自分の得意な領域やスキルを見つけ、伸ばすことが、ニーズに見合った高いレベルの提案につながっていく
【人事インタビュー】
時代の変化に対応する “次世代コンサルタント”育成の取り組み
デロイト トーマツ グループが長年の歴史の中で培ったノウハウを強みに、グローバルで通用するプロフェッショナル人材を育成してきたDTC。これから活躍する“次世代コンサルタント”を育てるための取り組みを、人事担当者の押切麻理子氏に聞いた。
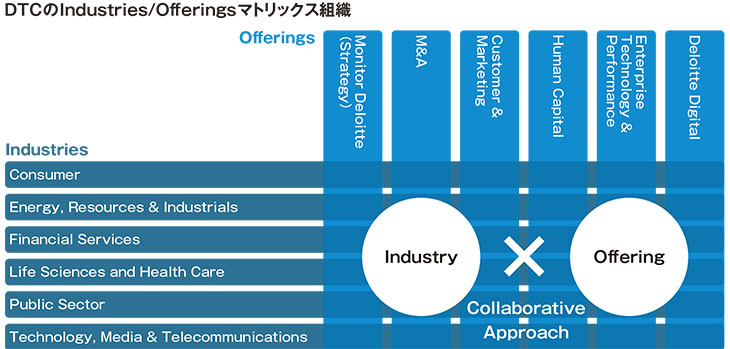
 デロイト トーマツ グループ 新卒採用チーム マネジャー
デロイト トーマツ グループ 新卒採用チーム マネジャー
押切 麻里子氏
「DTCでは、今後時代の変化に対応できる“次世代のプロフェッショナル”を育てるための仕組みや機会を多く提供しています」
そう話すのは、同社人事担当の押切氏。DTCの新入社員は入社後に約2カ月間の研修『BA(ビジネスアナリスト)ブートキャンプ』でビジネスパーソンとしての素地をつくった後、実際のプロジェクトに参画し、現場で経験を積んでいく。
「入社後数年は、数カ月単位のサイクルでさまざまな領域のプロジェクトにアサインされます。専門性の高い各分野のプロフェッショナルたちの下で働くことで、コンサルタントとしての基礎スキルを身に付けるとともに、各業界や分野について学ぶことができます。そしてさまざまな領域を経験した後、適性や将来を考え自分の専門領域を絞り込み、更にスキルを積み重ねていく成長モデルです」
その後は各プロジェクトのマネジャー、プロジェクト全体を取り仕切るパートナーへとキャリアパスを歩んでいく。
「代表の佐瀬をはじめ、社内では次世代の活躍に対する期待が最高潮に達しています。コンサルタントとしての総合力・実践力だけではなく、高い専門性を持つプロフェッショナルに育ち、これから先のDTCをつくっていってほしい。そう考えるマネジャーやパートナーが多く、若手の方々が挑戦できる機会も豊富に用意されています」
若手の成長を大きく促す仕組みと組織風土が、今後必要とされるコンサルタントへの成長を加速させる。
取材・文/ワードストライク 佐藤大介 撮影/大島哲二