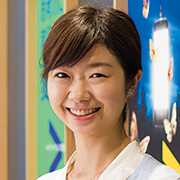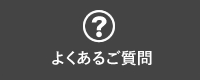-
- 記事
- インターンシップ特集
- コンサル
- アクセンチュア
- 最新技術やグローバルの知見を得ながら、挑戦を後押ししてくれる環境が最大の魅力
2017/5/31 更新 アクセンチュア
最新技術やグローバルの知見を得ながら、挑戦を後押ししてくれる環境が最大の魅力
- アクセンチュア
- インターン
- 技術
- 開発

アクセンチュア

テクノロジー コンサルティング本部
ITソリューション シニア・マネジャー
鉾之原 宰氏 【写真左】
大学卒業後、Webサービスを開発するベンチャー企業を経て、2005年にアクセンチュア入社。数々の大規模プロジェクトを牽引すると同時に、『エンジニア塾』の企画・運営を務める
テクノロジー コンサルティング本部
アナリスト
神谷喜穂さん 【写真右】
青山学院大学大学院理工学研究科修了後、2015年にアクセンチュア入社。1年目から大手機械部品メーカーの売上・在庫領域の分析・管理プロジェクトに携わっている。エンジニア塾参加経験者
――貴社では毎年、実践型のインターンシップ『エンジニア塾』を展開していますね。どのような主旨で実施しているのでしょうか?
鉾之原
アクセンチュアのソリューション・エンジニアが日々実行している仕事のエッセンスを体感していただきたいという主旨です。
与えられたビジネス課題から解決すべき問題点を抽出し、その分析を通じて解決策を練り、最適なソフトウエアの開発を実施する。同時にチームでワークすることの面白さ、そして難しさも体験してもらえる内容になっています。
神谷
私は3年前にエンジニア塾に参加したのですが、初日の朝から非常に印象的でした。
参加学生がとにかく明るくてエネルギッシュ。さらに衝撃的だったのがサポーター社員の方々でした。一人一人が強烈な個性を放っていました(笑)。
鉾之原
それも「アクセンチュアらしさ」の一つだからね(笑)。
アクセンチュアにはさまざまな分野で突出した得意領域を持つ、個性豊かな社員が本当に多いです。そういったメンバーのおかげで、私もいろいろな角度で物事を分析できるし、周りから学ぶこともよくあります。
ですがエンジニア塾はあくまでも学生の皆さんの自主性を重視しているから、手取り足取り教えません。それにチームメンバーのスキルや経歴はささまざまなので、チームとして効率良く作業できる役割分担を話し合ってもらうようにしています。
最終日までのプランも学生が自力で決めていたよね?
神谷
はい、自分たちが主体となって進めていく必要があるんだ、ということは早々に理解して、全員が納得できる役割分担を決めました。
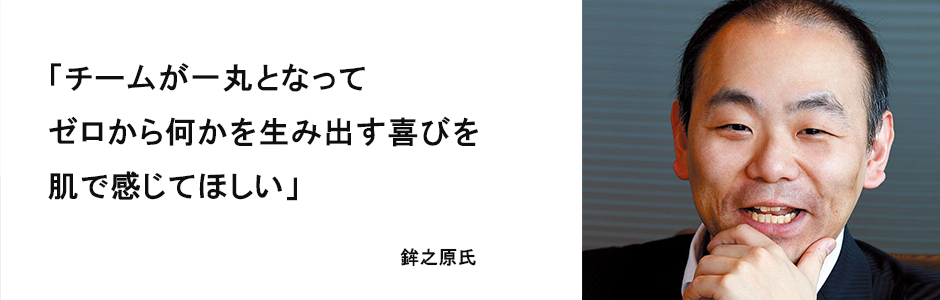
鉾之原
我々の会社では参画するプロジェクトが変わるたびに、新しいメンバーと仕事をするケースが多い。毎回、チーム・ビルド
が大切になるから、プロフェッショナルなチームワークも体験してほしいと思っているんだ。
確か神谷さんはリーダーを務めていたよね?
神谷
はい。私自身、やりたいと思ったし、チームメイトもバックアップしてくれました。チームとしてどう動くのが一番高い価値を出せるのか、何が最適な解なのか、メンバー全員で真剣に考えました。
『個々人の強みを活かして、チームとして最高の結果を出せればいいんだ』と教わりましたね。全員で同じゴールに向かい、最後まで楽しみながら学ぶことができました。
鉾之原
プログラミング未経験者が途中でギブアップしたこともないんだよね。
我々にとって一番重要なのは、ビジネス上の課題を解決すること。アクセンチュアはとりわけ新しいテーマや領域にチャレンジする集団だから、未知の領域にチャレンジするケースも日常的。
だからこそ、チーム内で互いの力を補完しながら結果を出すことにコミットしている学生たちを頼もしいな、と思いながら見ていますよ。
――貴社では近年どのような案件を多く手掛けているのですか?
鉾之原
社会的にも話題となっているAIやIoT、ロボティクス等への取り組みもいち早く進めてきましたが、デジタル・マーケティングに関する案件も増えています。
スマートフォンやタブレットなどモバイル端末が普及した今、これらのデータを用いてエンドユーザーにどのような働き掛けができるのか、どんな新規ビジネスを創出できるのかなどの課題を多くの企業は抱えています。アクセンチュアに期待されているのは、その解決策の提案です。
神谷
新しいことに挑むのが好き、という方がとても多いですよね。毎日のように「次はこういうプロジェクトにチャレンジしたい」といった話を聞きます。
私はサプライチェーン領域の開発業務に参画したいと思っていますし、将来的にはグローバルな案件にも挑戦してみたい。アクセンチュアの恵まれた環境を活かして成長していきたいですね。

――最後に、エンジニア塾の最大の魅力を教えてください。
神谷
未経験のことにチャレンジさせてくれるだけでなく、必要ならば道を示し、後押しもしてくれる点ですね。
実は私も最初はリーダーとしての戸惑いを覚えていました。そんな時にサポーターからアドバイスをいただいたんです。役割も経験値も違うメンバーを1つのチームとしてまとめていくには、最初に全員共通の目標をしっかり定めることが重要だよ、と。実行したら、ビックリするくらいチームが機能しました。
伝授していただいたチーム・マネジメントの秘訣は、入社後の今も活きています。最後に自分たちが作ったプログラムが想定通りに動いたのを見た時も本当にうれしかったですね。モノづくりの醍醐味を実感しました。
鉾之原
エンジニア塾では「課題に直面した時にチームで乗り越えていくことの面白さを知ってほしい」という点を重視しています。
我々はできる限りのサポートをするし、学生の皆さんには成長を持って帰ってほしい。この経験を通じてアクセンチュアをより深く知ってもらいつつ、ソリューション・エンジニアの魅力を感じ、参加者に新しい自分と出会えてもらえたらうれしいですね。

(取材・文/森川直樹、撮影/竹井俊晴)