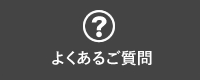ビジネスプロフェッショナルが解説
「真の企業力」を見抜く方法
会社の良しあしは「知名度」だけでは測れない。これから先も長く発展し続ける会社、急成長を遂げる可能性を秘めた伸びしろのある会社は、どうすれば見極められるのだろうか。企業経営、組織開発・採用のプロフェッショナルたちが、各社の事例を用いて「真の企業力」を見抜く方法を解説。インターンシップで確認すべきポイントも紹介する。

求められるのは時代の流れや顧客ニーズへの適応力
独自性を保ちながらも柔軟に変革しているかを確認して
日本貿易保険(以下、NEXI)は、貿易保険を通じて日本企業の海外展開を支援するために設立された日本政府の政策実施機関です。NEXIと同様に公的な立場から固有の事業を行う組織は複数存在しますが、NEXIが扱うのは民間の保険会社では対応が難しいリスクをカバーする公的な貿易保険。戦争や自然災害などの避けられない事象や、取引相手の代金不払いや破産などの発生により、日本企業が被る損失を補います。この貿易保険を通じて、日本の中堅・中小企業による小規模な輸出取引から、大手商社、メガバンク、日系メーカーといった日本を代表する企業による数千億円規模の海外の大型プロジェクトのファイナンスまで、あらゆる海外取引を支援しています。また、民間の損害保険会社と連携しながらプロジェクトを支援するケースもあるため、民間企業との結びつきはとりわけ強く、あらゆる企業と手を携えて日本企業の海外展開や日本経済の発展をサポートしている組織です。
NEXIにおける「成長」の大きな指標は、貿易保険を活用してくださる企業を増やすこと。公的機関であるため、利益の追求以上に、どれだけ日本企業の海外展開を支援できるかという点を重視しています。NEXIが年間で支援した案件規模の合計値を指す「保険引受実績」は、2019年度以降の5年間で約2兆円増加。23年度は約8兆円の実績で、前年比では約4.4%アップを記録。海外展開する企業への支援という事業を通じ、四半世紀の間成長を続けてきました。
直近では、NEXIが直接保険を提供できない国に現地法人を持つ日本企業の支援にも尽力しています。海外支店を持つ民間の保険会社と連携し、NEXIの保険を代わりに販売してもらうという手法で顧客を拡大。これまで未進出だった国へのさらなる進出を目指し、顧客ニーズの調査・分析をしながら参入の可能性を探っています。ある案件では、当時新卒入社1年目の職員が自ら手を挙げて案件を推進するなど、若手でも挑戦の意欲がある職員は早くから主軸として活躍できるのもNEXIの特徴の一つです。
このように支援の幅を拡大するとともに、政策実施機関として最新の政策に関わる取り組みにも注力しています。現在は再生可能エネルギーの利用促進や、資源エネルギー・食料の安定調達などの国家が重要視する分野に取り組むことで、社会的使命の達成を目指しています。
一人一人のスキル・知識の向上と業務効率化の推進で
ニーズの増加や多様化に順応できる存在に
NEXIでは、職員個人と会社の成長のため、一人一人のスキル・知識と生産性の向上に力を入れています。スキル・知識の面では、15年から始めた新卒採用で入社した若手の職員が全職員の約4割と多い観点からも、キャリア支援・研修制度の充実化にこだわっています。例えば、業務に携わる上で有益な資格の取得・研修受講のための費用は会社が全額を負担しますし、業務に直結する専門知識の習得は業務の一部と見なし、業務時間内で研修の受講が可能です。また業務に直接関係がなくとも、自己啓発を目的に受講する研修であれば費用の8割を会社が負担します。加えて、24年度からスキルアップ手当という新たな制度を導入しました。会社の定める特定の資格取得や特定の試験における一定以上のスコアの獲得に応じて、基本給に上乗せしてインセンティブが支給される制度です。これらの制度は多くの職員が利用しており、働きながら学び続けられる環境が整っています。
生産性の面では、AIによる業務効率化を鋭意推進中。業務効率化に特化した部署を新設し、効率化をテーマとしたコンテストの開催やAIの試験導入もスタートしました。年に1回開催されるコンテストは、各部署の個人やチームが特に効率化を図れた事例をエントリーし、それぞれが発表するというもの。直近では、これまで約2時間かかっていた業務が5分にまで短縮された事例が出てきており、各部署内で大幅な時間短縮が実現しています。他にも、既存業務の自動化について新設部署に相談し、改善提案を受けられる仕組みができ、多くの職員が活用しています。
こうした取り組みに注力しているのは、「時代の流れに合わせて柔軟に変革し続けること」が企業の長期的な成長において最重要と考えているからです。企業に属する一人一人に豊富なスキルや知識があれば、案件ごとに柔軟な発想を持って課題を解決へと導けるでしょう。また、AIの導入で業務効率を高めることで、企業として余力が生まれてきます。キャパシティーが増えればより多くの日本企業を支援できますし、ビジネスやニーズの理解、新たな課題解決手法の創出にエネルギーを使うことができるのです。
もちろん、全てを変えるのが理想的ということではありません。時間をかけて築き上げてきた企業の独自性は保ちつつも、時代やビジネスの流れに合わせて提供する商品や制度を改善・拡充できるか、その姿勢があるかどうかということは、企業の成長可能性に直結します。これから本格的に就職先を探す皆さんも、こうした観点で企業を分析してみると、きっと共に成長していける企業と出会えるでしょう。
制作担当/松澤美喜

毎年グループワーク形式で1dayインターンシップを開催。資料を基にメンバー間で議論し、融資保険取引の一連のプロセスを疑似体験するというプログラムだ
インターンシップMUST DOリスト
-
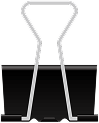 1
1企業が発信する
メッセージを読み取るインターンシップ当日のワークショップや紹介される事例は、企業が学生に一番伝えたいことの結晶である場合が多いでしょう。その企業が何を伝えたいのかを意識することで、会社独自の視点や、大切にしている理念・価値観が見えてきます。
-
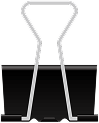 2
2職員と積極的に交流し
多角的に情報を得る現場の職員と直接話すことができる、貴重な機会であるインターンシップ。積極的に職員と交流し、その企業の雰囲気や社風、先輩のキャリア事例、働き方の選択肢など、インターネットからは知ることのできないリアルな情報をキャッチしてみてください。
-
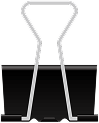 3
3できる限りリラックスした
状態で取り組む「企業に対して良い印象を与えなくてはならない」と思うかもしれませんが、あまり気を張らずに楽しんでほしいです。緊張せずに自然体で参加することで、十分な学びを得られますし、現場の職員と自身のマッチング度合いもしっかりと測れるはずです。