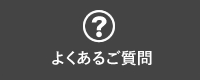インターンシップ参加×セルフチェックで準備する
「自分らしく働く」の始め方
「自分らしく働く」って素敵だけど、そもそも「自分らしく」って何だろう?働く上で自分が大事にしたいことは何なのか、何のためなら頑張れるのか、何に喜びを感じるのか……インターンシップを通して自分のことを深く知るための方法や、先輩たちが就職後に知った「自分らしく働く」への答えを紹介します。
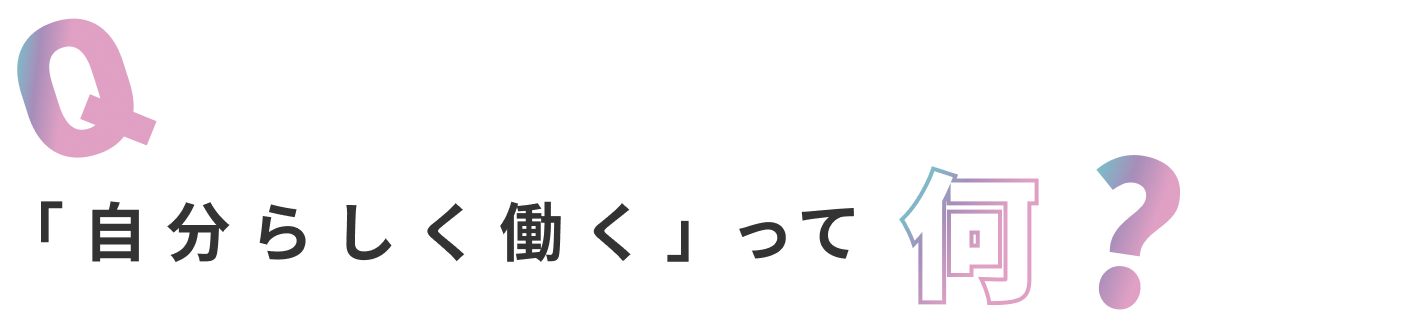
自ら求めて選択したキャリアを
開拓する中で楽しみを見いだす

官公ソリューション第二本部
官公システム第九部
氏
キャリアの目標を自分で定め、自ら道を開拓していく。それが私にとっての“自分らしく働く”です。日立製作所に入社を決めたのは、5日間の冬季インターンシップに参加した際に、「枠にとらわれない柔軟な風土が自分に合う」と感じたからでした。今でも、グループワーク中に先輩社員の方々が成果を最大限に追い求めるべく、3日かけて固めたアイデアを迷うことなく捨て、方向転換したときのことを覚えています。「歴史ある大手企業でありながら、柔軟な発想を持つ人々が活躍しているのか」と驚くと同時に、固執しない風土に自分らしく働けるイメージが持てました。また、ジョブ型のキャリア形成により、自分でキャリアパスを決めて挑戦していけることも魅力でした。実際、入社してから「何がしたいか」を見つめる機会を多く与えられ、意志を持って働く日々を送っています。
入社以来4年間、厚生労働省における年金分野のシステム開発を担当し、法改正に伴う改修や機能改善を手掛けてきました。思い出深いのは、去年担当した年金の給付・納付の両データを連携させる案件にて提案から開発まで一貫して手掛けたことです。当初、お客さまは業務に必要な一部データの連携のみを要望されていたのですが、私は周辺データをも一挙に連携するシステムを提案しました。システムを利用する他部署にもヒアリングを行った結果、幅広いデータの連携が求められていたことがわかったためです。小さなシステム改修を繰り返すより、このタイミングで大きく改修するほうが結果としてコストを軽減でき、組織全体に役立つものになるはず。先のことを見据えた実益の高い改修になることは明らかでしたが、一方で大幅に予算が超過することに難色を示されてしまいました。そこで私は視点を変え、該当システムを扱う全ての部署に関わる大規模プロジェクトとして推進することに。上司や先輩からアドバイスを受け、力を借りながらではありましたが、より権限を持つ方と合意形成をすることで数億円規模の予算を確保し、無事にシステムをリリースできました。若手にもスケールの大きな案件を任せる風土があることはもちろん、上司や部長など周囲の方々からの支援もあり、やり抜くことができたと思います。

研修・教育制度を積極的に活用し
チャンスをつかむ準備を怠らない
自分らしいキャリアを築くためには、社内の研修制度を積極的に活用し、スキルを磨くことが重要だと考えています。多様な選択肢が用意されていても、スキルや資格の有無によってはチャンスを逃してしまうこともあるでしょう。私自身は語学力に磨きをかけるべく、毎年TOEICの試験を受けていますし、最近は年金アドバイザーの資格も取得しました。自分のやりたいことを実現するためには、「任せよう」と思ってもらえなければ声がかかることはありません。仕事上の結果をはじめ、できる限りの準備を日々続けることで、自分の武器は磨かれていくと思います。
日立製作所では、多様な教育研修を提供しており、専門教育機関の日立アカデミーでは、会社が資金を援助し、興味がある分野を勉強できます。また、私の場合は、所属している部署の業務を調整しながら他の部署の業務にも挑戦できる社内副業制度を活用し、本業以外で挑戦したい分野のプロジェクトに参画中です。DX部署にて新規領域のビジネスアイデアを検討するチームの一員として、新たな知見を増やしながら可能性を広げています。
さまざまな研修や他事業部との協創を通して、数々のプロジェクトを成功に導いたゼネラリストや卓越した技術力を持つスペシャリストなど、多くの人と出会う機会がありました。そのおかげで、イメージできるキャリアの選択肢は広がりましたし、働く軸も定まったように思えます。日立製作所のように何事も自分で選べる環境があり、自己成長を続けられさえすれば、自分らしく働き続けられるでしょう。
制作担当/岩城篤
自分の価値観を知るために
インターンシップで確認すべきこと三つ
-
1
社内の教育・研修制度が
どの程度充実しているか利益に直結しない教育・研修のリソースが充実している企業は、人材を大切にしているはずです。例えば、入社何年目まで研修制度を用意しているか確認することで、中長期的な人材育成に取り組んでいるかを判断しやすくなります。
-
2
自分がその企業で働く姿を
想像することができるかインターンシップは、社内の雰囲気や働く人を直接見るチャンスです。会場に向かうときに通りがかったフロアの雰囲気や社員の表情、デスクの整頓具合などから、会社の風土が自分に合うかを直観的に判断してみましょう。
-
3
質問しやすい環境があり
心理的安全性を感じられるか質疑応答の時間では、社員がどう働きかけてくれるか着目してみてください。将来的に上司や先輩になる方々がどのようなコミュニケーションを取ってくれるのか。質問や相談がしやすい風土が醸成されているかという判断材料になるでしょう。