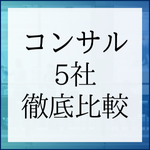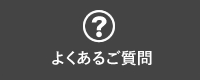2025/12/23 更新 選考対策
ガクチカ(学生時代に力をいれたこと)とは?テーマの探し方、構成、書き方を例文付きで解説!
- 2028卒
- 28卒
- ES対策
- ガクチカ
- 就活
- 面接対策
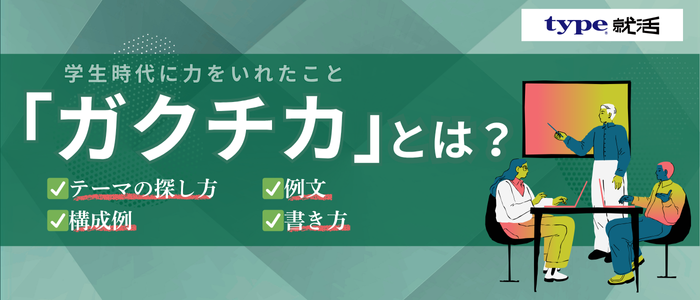
みなさんこんにちは、type就活です!
「ガクチカって何を言えばいいんだろう...」
「自分の経験なんて大したことないかも...」
「どうやって書けば印象に残るんだろう...」
就活を始めると、多くの学生がこんな不安を抱えます。
この記事では、就活で必ず問われる「ガクチカ(学生時代に力をいれたこと)」について、選考を突破するための具体的な書き方を解説します。
どんなテーマを選べばいいのか、どういう構成で書けばいいのか、どのような表現が効果的なのか——
これからガクチカを作る皆さんの不安を解消し、自信を持って選考に取り組める充実のコンテンツとなっております!
ぜひ最後までご覧ください!
ガクチカを作るために 目次
1.ガクチカとは?
- ガクチカ=「学生時代に力をいれたこと」
「ガクチカ」とは、就職活動において頻繁に問われる「学生時代に力を入れたこと」を意味する略語です。
ES(エントリーシート)から最終面接まで、選考のあらゆる段階で問われる可能性があり、就職活動における最も重要な準備事項の一つと言えます。
ESでは「400字程度で」、面接では「1分程度で」などの形式で、主に大学時代に力を入れて取り組んだ活動について伝えることが求められます。
- なぜ企業はガクチカを問うのか?
企業がガクチカを通じて知りたいのは、主に以下の3つです。
1. 学生の能力と成長過程
◦困難な状況でどのように考え、行動したか
◦課題をどのように解決に導いたか
→そのプロセスから、入社後の活躍可能性を判断しています。
2. 価値観と人柄
◦どのようなことに興味を持ち、何に価値を置いているか
◦企業の社風との相性
◦組織で継続的に努力できるか
3. 経験の再現可能性
◦過去の経験は入社後も再現できるか
→具体的な状況、役割、成果からそれを判断しています。
→また論理的思考力とコミュニケーション能力も同時に確認しています。
企業はガクチカと合わせて自己PRや志望動機なども総合的に評価し、あなたが採用される企業や職種にフィットするかを判断しています。
- 評価されるポイント
ガクチカで高い評価を得るためには、ESと面接それぞれで異なるポイントを理解し、適切な準備をすることが重要です。
■ESでのポイント
・論理的な文章展開
・経験と能力を効果的に伝える構成
・文法的に正確な日本語表現
・字数制限内での簡潔な表現
■面接でのポイント
・深掘り質問に一貫性をもって回答できる準備
・具体的な状況や思考過程のわかりやすい説明
・他の経験との繋がりや成長ストーリーの展開
・非言語コミュニケーション(表情、姿勢、声のトーン)
両方に共通するのは「具体性」と「一貫性」です。
抽象的な表現や誇張は避け、実際の経験に基づいた具体的なエピソードを一貫した論理で伝えることが評価のポイントになります。
2.ガクチカの書き始めかた
- ①テーマ探しの方法
「部活もしていない」「留学経験もない」「アルバイトも普通のことしかしていない」—
多くの就活生がこのように悩み、ガクチカのテーマが見つからないと感じています。
しかし、実はあなたの日常の中に、十分魅力的なガクチカになる経験は必ず眠っています。
ここでは「何も書くことがない」と感じている方に向けて、価値ある経験を発掘するステップを紹介します。
【STEP1】小さなものも含めた経験の棚卸し
まず以下のような問いかけから、思いつく限りの経験をリストアップしてみましょう。
この段階では「大したことじゃない」と思う小さな経験も含めることが重要です。
■日常生活の中での工夫
・一人暮らしで効率化したこと
・勉強法で工夫したこと
・家計やスケジュール管理での取り組み
■人間関係での出来事
・グループワークでの役割
・ルームメイトとの関係調整
・友人との小さなプロジェクト
■アルバイトでの小さな役割
・マニュアル作成への協力
・新人研修のサポート
・シフト調整での提案
■大学での学び
・関心を持った授業とそこでの取り組み
・レポート作成で力を入れたこと
・自主的な学習グループでの活動
■趣味や特技の深掘り
・継続している趣味とその上達過程
・SNSでの発信活動
・自己流で始めた小さなチャレンジ
リストアップした経験を以下の2つの視点で振り返ってみましょう。
■熱量があった経験かどうか
・時間を忘れて取り組んだか?
・もっとやりたいと思ったか?
・誰かに熱心に説明したくなったことはあったか?
■何らかの困難があった経験かどうか
・思い通りにいかなかったことがあったか?
・工夫や試行錯誤が必要だったか?
・自分の限界に挑戦したと感じていたか?
この2つの視点でチェックがついた経験は、結果の大小にかかわらず、あなたが思っているより価値がある可能性が高いです。
「それって誰でもやっていること」「大したことじゃない」と思っている経験こそ、実は価値が隠れています。
以下の問いかけで、その経験の価値を掘り起こしてみましょう。
「比較」の視点: 周りの人と比べて、あなたならではの取り組み方はあったか
「数値」の視点: その経験で何か数字で表せる変化はあったか(例:効率が20%上がった)
「過程」の視点: 取り組みの中で、どんな判断や工夫があったか
「成長」の視点: その経験の前後で、あなた自身に何か変化はあったか
【具体例:普通のアルバイトを価値ある経験に変える例】
「ファミレスでのアルバイト」を例に、価値ある経験に変換するプロセスを見てみましょう。
変換前:「ファミレスで2年間アルバイトしていました。特に成果はありません。」
問いかけと気づき:
・勤務中に困ったことはなかったか? →「実はピーク時の回転率に悩んでいた」
・何か工夫したことはないか? →「テーブルセッティングの順序を変えてみた」
・誰かと協力して取り組んだことは? →「新人スタッフにコツを教えるミニマニュアルを作った」
・数字で表せる変化は? →「私のシフトではテーブル回転率が15%上がった」
変換後: 「ファミレスで2年間アルバイトし、ピーク時の客席回転率向上に取り組みました。セッティング手順を効率化し、その方法を新人向けマニュアルにまとめた結果、私のシフトでは回転率が15%向上。店長から評価され、新人教育も任されるようになりました。」
【STEP4】企業視点で価値を言語化する
発掘した経験を企業が評価する能力(主体性、課題解決力、チームワークなど)と結びつけて言語化しましょう。
発掘した経験: 「ファミレスの回転率向上に取り組んだ」
企業視点での言語化:
・効率化への意識: 「ピークタイムという限られた時間の中で、より多くのお客様に快適にご利用いただくために、業務の無駄を省き、効率的なオペレーションを常に意識していた。」
・顧客視点: 「お客様の待ち時間を少しでも短縮し、満足度を高めるために、先読みの行動やスムーズな連携を心がけた。」
・問題解決能力: 「回転率が伸び悩む原因を分析し、現状のオペレーションにおける課題を発見。その解決策として、テーブルセッティングの順序変更や新人教育マニュアルの作成を実行した。」
・チームへの貢献: 「個人だけでなく、他のスタッフと協力しながら目標達成を目指した。新人スタッフへの教育を通して、チーム全体の能力向上にも貢献した。」
・成果へのコミットメント: 「自身の工夫によって、実際に客席回転率が15%向上するという具体的な成果を出すことができた。これは、目標達成への強い責任感と行動力を示すものだと考えている。」
このように、一見すると平凡に思える経験も、視点を変えると貴重なガクチカのテーマになります。
自分の「当たり前」に価値があることを信じて、経験を丁寧に言語化していきましょう。
- ②ガクチカの構成
ESや面接で説明しやすい、論理的な構成を心がけましょう。
基本的なガクチカの構成は以下の5つの要素で成り立ちます。
(参考の文章量をパーセンテージで表示しています。)
1. 前提となる状況(10%)
・いつ、どこで、どのような立場だったか
・なぜその活動に参加したのか
・当時の環境や条件
2. 目標と動機(15%)
・何を達成しようとしたのか
・なぜその目標を設定したのか
・どのような思いがあったのか
3. 直面した課題と障害(20%)
・どのような困難に直面したか
・なぜその課題が発生したのか
・その時の自分の感情や周囲の反応
4. 解決のための思考と行動(40%)
・どのように課題を分析したか
・どのような解決策を考えたか
・具体的にどう行動したか
・工夫したポイントは何か
5. 結果と学び(15%)
・どのような成果が得られたか
・数字で表せる実績はあるか
・その経験から何を学んだか
・どのように成長したか
この構成は「論理的思考」に基づいており、企業が確認したい「思考力とその再現性」を効果的に伝えられます。
- ③表現・書き方のコツ
ガクチカの表現や書き方に絶対的な正解はありませんが、以下のポイントに注意すると読みやすく説得力のある文章になります。
【避けるべき表現】
文のねじれ:特にESでは字数制限を気にするあまり1文が長くなりがちです。主語と述語の対応に注意しましょう。
「御社」と「貴社」:書き言葉「貴社」が正しいです。話し言葉では「御社」を使用します。
強調表現の多用:「非常に」「かなり」などの強調表現は控えめに使用しましょう。過剰なアピールは逆効果です。
冗長な表現:「〜することができた」→「〜できた」、「〜ということが」→「〜が」など、簡潔な表現を心がけましょう。
【効果的な表現テクニック】
数値化:「大幅に向上」ではなく「20%向上」など、具体的な数字で表現
比較表現:「以前は〜だったが、取り組み後は〜になった」と変化を明確に
感情表現:「悔しさを感じた」「達成感があった」など、人間味のある表現も適度に
- ④ガクチカの添削と改善
ガクチカが一通り完成したら、必ず第三者に読んでもらい添削を受けましょう。
なぜなら自分の経験を限られた字数でまとめると「論理の飛躍」が生じやすいからです。
【添削のチェックポイント】
1. 第三者が読んでも状況が理解できるか
2. 文脈に飛躍はないか
3. 主張と根拠が明確か
4. 自分の役割と貢献が具体的か
5. 企業が知りたい情報が含まれているか
改善前の例:
私は大学2年次から音楽サークルの代表を務めました。入部当初は人間関係に悩み、退部も考えましたが、先輩の勧めで広報担当になりました。SNSを活用した結果、新入生が30名増え、練習場所が足りなくなりました。
そこで私は大学の施設課と交渉し、使用可能な教室を増やしました。しかし、楽器の音漏れが問題となり、一時は活動停止の危機に。サークル内では意見が対立し、メンバーの不満が高まりました。この問題を解決するため、全体ミーティングを開催し、活動方針を見直しました。
結果として、近隣の音楽スタジオと提携することに成功。打ち込み系の音楽制作にも挑戦し、大学祭では過去最高の来場者数を記録しました。この経験から、困難な状況でも諦めず、常に新しい視点で問題解決する力が身につきました。
改善後の例:
私は大学2年次から音楽サークルの代表を務めました。当時の目標は「より多くの学生に音楽の楽しさを伝える」ことであり、新入生の募集に力を入れました。募集の課題としてサークルの認知度不足と活動内容の不透明さを認識しました。対応策としてSNS運用を刷新し、週3回の定期投稿と演奏動画の配信を開始しました。
その結果、新入生が前年比150%となり、予想外の課題として練習場所の不足が発生。私は大学施設課と粘り強く交渉し、使用可能教室を2室から5室に増やしました。しかし次に音漏れ問題で近隣から苦情が入り、活動停止の危機に直面。サークル内では「音量制限」派と「自由な表現」派で対立が生じました。
この事態を打開するため、全メンバーの意見を聞く場を設け、サークルの本質的な目的を再確認。その上で近隣の音楽スタジオと月額割引契約を結び、同時にDTM(デスクトップミュージック)制作にも活動を広げる方針転換を提案しました。結果、活動の幅が広がり、大学祭では来場者数が前年比40%増の500名を記録。この経験から、制約をチャンスに変える発想力と、対立を調整するリーダーシップが身につきました。
3.良いガクチカの例文3選
実際の例文を見ることで、効果的なガクチカの書き方がより明確になります。以下に3つの異なるタイプの例文を紹介します。
- 例文1:アルバイト経験(課題解決型)
私はカフェでのアルバイトに2年間従事し、マネジメント業務も担当しました。入社半年後、店長から「新規顧客の獲得とリピーター率向上」という課題を任されました。
まず現状分析のため、顧客100名にアンケートを実施。「雰囲気が良い」「コーヒーが美味しい」という評価の一方、「メニューが少ない」「Wi-Fiがない」等の不満も発見しました。さらに、顧客データを分析したところ、近隣オフィスに勤めるビジネスパーソンや大学生の利用が少ないことが判明。
そこで①若者向け季節限定メニューの開発、②Wi-Fi設置、③試験期間中の営業時間延長を店長に提案。コスト面での懸念があったため、投資回収計画も含めた企画書を作成し、承認を得ました。
実施後3ヶ月で新規顧客が15%増加、特に20代の来店が25%向上。リピーター率も20%上昇し、売上は前年同期比で18%アップを達成。この経験から、顧客視点での課題発見力とデータに基づく改善提案力を身につけました。
このガクチカは実績をわかりやすく伝えられており、優秀さをよくアピールできています。
数字や事実を端的に述べており、論理が飛躍している箇所もあまりみられない点がgoodです。
一方で経緯や理由付けの部分は大きく省かれており、面接では詳細なコミュニケーションの内容や実施中の困りごと等について深掘りされることになるでしょう。
- 例文2:サークル活動(リーダーシップ型)
私は40名規模の軽音楽サークルで3年間活動し、最終年度は代表を務めました。代表就任時、サークルは「公演の質の低下」と「メンバーのモチベーション低下」という課題を抱えていました。
原因を探るため、全メンバーと1対1の面談を実施。その結果、①練習時間の不足、②技術指導の機会不足、③目標の不明確さが主要因だと特定しました。特に問題だったのは、レベルや目的の異なるメンバーが混在しているにも関わらず、画一的な活動を強いていたことでした。
そこで「多様性を活かした成長の場の創造」を新ビジョンとして掲げ、①技術レベル別の練習グループ制導入、②月例の技術共有ワークショップ開催、③半年ごとの明確な目標設定の3つの改革を実行。特に難しかったのは古参メンバーの反発でしたが、個別に時間をかけて対話し、「変化の必要性」への理解を得ることに注力しました。
1年間の取り組みにより、公演での観客満足度が68%から89%に向上。メンバーの継続率も45%から82%に改善しました。この経験から、多様なメンバーの強みを活かし、共通目標に向かって組織を導くリーダーシップを学びました。
こちらは先ほどと異なり、人と組織を相手としたガクチカです。
このガクチカでは鍵カッコを用いてこの話題のキーワードを分かりやすく示せており、ユニークな内容ながら端的に伝わりやすい文章になっています。
組織改善系のガクチカでは「具体的な人の例」「周りの反発」「人と相対する際気を付けていたこと」等が面接での頻出深掘りとなります。
- 例文3:プロジェクト経験(協働型)
私はゼミの活動で地元商店街活性化プロジェクトに1年間取り組みました。10名のチームで「若年層の集客アップ」を目標に掲げ、私はデータ分析と企画立案を担当しました。
まず地域住民200名にアンケート調査を実施。その結果、商店街の認知度は高いものの、「古い」「必要なものがない」というイメージが若年層に定着していることが判明。さらに商店主15名へのインタビューから、「若者向け施策への意欲はあるが、何をすべきか分からない」という実態も浮かび上がりました。
この「意欲はあるが方向性が見えない」という状況を打破するため、チーム内で激しい議論を重ね、「週末マルシェ」という企画を立案。私は特に、①出店者の選定基準の策定、②SNS広告の費用対効果分析、③来場者動向の可視化に注力しました。途中、チーム内で広告予算の使い方について意見対立が生じましたが、データに基づく提案を行い、最終的に合意を形成できました。
初回マルシェには目標の120%となる600名が来場、うち67%が20〜30代という成果を達成。アンケートでは「商店街のイメージが変わった」との回答が78%を占め、定期開催が決定しました。
この経験から、異なる視点を持つ人々との協働力と、データに基づく意思決定の重要性を学びました。
このガクチカで扱われる「年齢が離れている方々との折衝」も面接官にウケがいいテーマの1つです。
自身の取り組みとクライアントとの関わりがバランスよく記述されており、工夫が伝わるガクチカになっています。
4.ガクチカのよくある疑問
- 高校時代のエピソードでもいいの?
基本的な考え方
基本的には大学時代の経験を中心に考えましょう。企業は「最近の」あなたの能力や思考を知りたいと考えています。
例外的な状況:
・ESで「学生時代全般のエピソード」と明記されている場合
・高校時代に特筆すべき実績や経験がある場合(全国大会出場、起業経験など)
・大学での活動が限られている場合
面接での対応
面接で「ガクチカを教えてください」と聞かれた場合は、まず大学時代の経験を話しましょう。
複数のエピソードを求められた場合は、「高校時代になりますが、もう一つ印象に残っている経験があります」と前置きしてから話すのがベストです。
- 常体?敬体?
ESの場合
どちらでも問題ありませんが、字数制限がある場合は常体(〜である、〜した)の方が文字数を節約できるためおすすめです。
面接の場合
面接では基本的に敬体(〜です、〜ました)で話しましょう。
アンケート・メッセージ欄
企業の方へのメッセージや感想を記入する欄は、必ず敬体を使用しましょう。
- 人柄も示せと言われることがあるんだけど...?
基本的な考え方:
ガクチカでは、まず企業が知りたい「あなたの能力や思考力」を具体的な経験を通して伝えることが最優先です。
しかし、選考が進むにつれて、企業はあなたの「人となり」や「価値観」にも興味を持つようになります。
ESでの対応
ESは、字数制限がある場合が多いため、まずは実績や経験といった具体的な内容を簡潔に伝えることを優先しましょう。
自己PR欄など、別途人柄をアピールできる欄が設けられている場合もあります。もし字数に余裕があれば、経験を通して得られた学びや、その経験に対するあなたの動機・熱意を簡潔に加えることで、人柄をにじませることも可能です。
例: (字数に余裕がない場合)
〇〇サークルで副代表を務め、会員数増加に貢献しました。具体的には、SNSを活用した広報活動と、初心者向けの体験イベントを企画・実行しました。結果、新規会員数を前年比20%増を達成しました。
(字数に余裕がある場合)
〇〇サークルで副代表を務め、会員数増加に貢献しました。元々、〇〇が好きだったため、もっと多くの人に〇〇の魅力を伝えたいと考え、会員数増加を目標に活動しました。具体的には~(上記に同じ)~結果、新規会員数を前年比20%増を達成しました。この経験を通して、目標達成のためには、周囲を巻き込み、主体的に行動することの重要性を学びました。
面接での対応
面接は、ESでは伝えきれなかった「あなたの人となり」を深く理解してもらう絶好の機会です。
面接官は、あなたの言葉遣いや表情、熱意を通して、あなたがどのような人物なのかを見極めようとしています。
ガクチカを説明する際は、ESで伝えた経験をベースに、経験を通して感じたこと、学んだこと、そして何故その経験に打ち込んだのかといった、あなたの内面的な部分を積極的に言葉にしましょう。
- ガクチカで嘘をついてもバレない?
基本的な考え方:
ガクチカで嘘をつくことは避けるべきです。
短期的に見ればバレないように思えるかもしれませんが、長期的に見るとリスクが非常に高く、最終的には自分自身を苦しめることになります。
嘘がバレるリスク
ES(エントリーシート)の場合
・矛盾点が見つかる: 複数の設問や他の書類(履歴書など)との間で、内容に矛盾が生じる可能性があります。企業は提出された書類全体を総合的にチェックするため、小さな矛盾も見逃しません。
・深掘り質問への対応ができない: ESに書かれた内容をもとに、面接で深掘り質問をされることが想定されます。嘘の内容は詳細に説明することが難しく、言葉に詰まったり、曖昧な回答になったりすることで、嘘が露呈する可能性があります。
・企業調査でバレる: 企業によっては、ESの内容について裏付け調査を行う場合があります。特に、実績や役職など具体的な情報を記載した場合、事実確認が行われる可能性もゼロではありません。
面接の場合
・矛盾した言動が出る: 面接官は、あなたの言葉だけでなく、表情や態度、声のトーンなど、様々な要素から総合的に判断します。嘘をついている場合、どうしても不自然な言動が出てしまい、経験豊富な面接官には見抜かれる可能性が高いです。
・深掘り質問への対応ができない: 面接官は、あなたの回答に対して様々な角度から質問を重ねることで、内容の信憑性を確認しようとします。嘘の内容は、深掘りされるほど綻びが出やすく、論理的な矛盾や説明の曖昧さから嘘がバレてしまうことがあります。
・予期しない質問: ちょっといじわるな質問をすることで、あなたの反応を見る面接官もいます。動揺したり、焦ったりする様子から、嘘を見抜こうとする場合があります。
嘘をつくことのデメリット
・信頼を失う: もし嘘がバレてしまった場合、企業からの信頼を完全に失います。選考に落ちるだけでなく、今後の就職活動にも悪影響を及ぼす可能性があります。
・精神的な負担になる: 嘘をつき続けることは、精神的な負担が大きいです。常に嘘がバレないかという不安を抱えながら選考に臨むことになり、本来の実力を発揮することが難しくなります。
・自己分析の機会損失: ガクチカは、自分自身の経験を振り返り、成長をアピールする絶好の機会です。嘘をついてしまうと、自己分析が不十分になり、成長の機会を逃してしまうことになります。
正直であることのメリット
・信頼関係を構築できる: 正直に話すことで、企業との信頼関係を築くことができます。企業は、嘘偽りのない、ありのままのあなたを知りたいと思っています。
・精神的な余裕を持てる: 正直に話すことで、精神的な余裕を持って選考に臨むことができます。自信を持って自分の言葉で語ることができ、本来の実力を発揮しやすくなります。
・自己PRの質が高まる: 正直に自分の経験を振り返ることで、自己PRの質を高めることができます。嘘のない言葉は、相手の心に響きやすく、より効果的なアピールにつながります。
もし、自信を持って話せるガクチカがないと感じているなら
嘘をつくのではなく、過去の経験の中から、アピールできる要素を探し出すことに注力しましょう。
些細な経験でも、そこから得られた学びや成長を具体的に語ることで、十分に魅力的なガクチカになります。
また、嘘ではなく、多少の脚色や強調は許容範囲と考えることもできます。ただし、事実に反する内容や、誇張しすぎた表現は避けるべきです。
5.おわりに
ガクチカは、「あなたという人間を知るための窓」です。
派手な実績や肩書きがなくても、自分の経験を深く掘り下げ、そこから学んだことを誠実に伝えることで必ず評価されます。
最も大切なのは「自分らしさ」です。他人のガクチカを参考にするのは良いことですが、最終的には自分の言葉で自分の経験を語ることを忘れないでください。
就活は自己分析の絶好の機会でもあります。ガクチカを作成する過程で、自分の強みや価値観、今後のキャリアについても考えを深めていきましょう。
一人で悩まず、友人、先輩、キャリアセンターなど、周りのリソースを積極的に活用してください。
そして何より、自分の経験に自信を持って、就活に臨んでください!
6.就活を頑張りたい方へ!おすすめイベント
スケジュール通りに進めるだけでなく、効果的に準備を行いたい場合は、就活イベントへの参加がおすすめです。
type就活では、様々なニーズにあわせたイベントが沢山開催されています。
なかには、企業研究に役立つイベントも!
早めの段階から就活イベントに参加し、有利な就職活動を始めてみましょう。
■企業による業界研究セミナーの情報はこちら
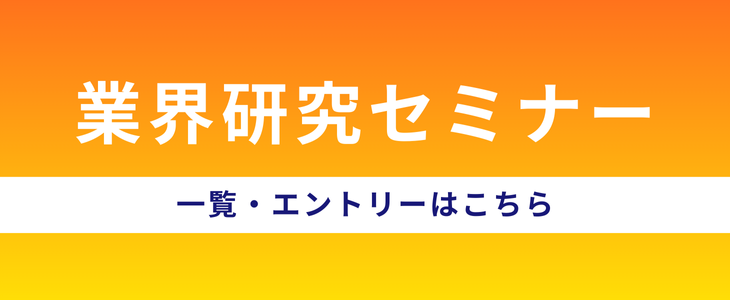 |
■選考対策イベント・合説の情報はこちら
 |
■就活を有利に、余裕を持って進めたい方へ!
就活はやることが多く、情報も溢れているので、その中から本当に自分に必要な情報だけを取捨選択していくことは、非常に大変だと思います。
そのため、「就活生のスケジュールに合わせたイベント情報・大手企業からのスカウト、インターン情報や選考情報」を効率よく手に入れられる、というのが理想的ではないでしょうか?
type就活では、そんな忙しい就活生のために、必要な情報を皆様にまとめてお届けしています。
月曜:新しく公開されたイベントやインターン情報
金曜:就活で必要な情報のコラム
※情報が更新されている可能性がございます。予めご了承ください。
就活生の皆様は、type就活に登録をするだけ!
興味のあるイベントやインターンシップ、選考情報があれば、ぜひエントリーください!就活生のスケジュールに合わせて情報を発信していますので、「もっと早く動けばよかった…」ということがなくなるでしょう。就活を少しでも有利に、余裕を持って進めたい方は、ぜひtype就活にご登録ください!
→業界・企業研究の選考対策記事はこちら
各業界のリーディングカンパニーの社員の声が多数掲載
→業界研究一覧 (各企業の社員のインタビュー記事)
就職活動をこれから始める方におすすめ
→企業研究がしたい方はこちら
- 執筆者
執筆:S.I.(東北大学4年 / type就活インターン)
大学3年次よりtype就活インターンに従事。現在はゼミでの卒論執筆に苦戦中。自身の就職活動で感じたリアルな悩みや役に立つ豆知識をtype就活のコンテンツを通して皆さんにお届け。
公式X:https://x.com/typeshukatsu
公式Instagram:https://www.instagram.com/typeshukatsu/
監修:type就活編集部 増野杏奈
株式会社キャリアデザインセンター入社後、年間20件以上のイベント運営や就活記事執筆など、type就活のサービス運営を担当。
入社8か月で、累計2000PVを超える記事を執筆するほかオリジナルイベントを6件企画し、就活生向けの情報発信を行う。