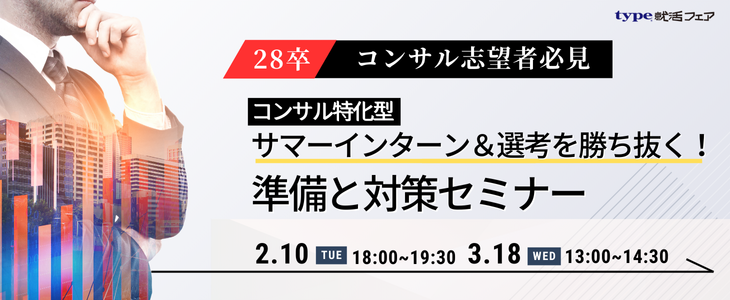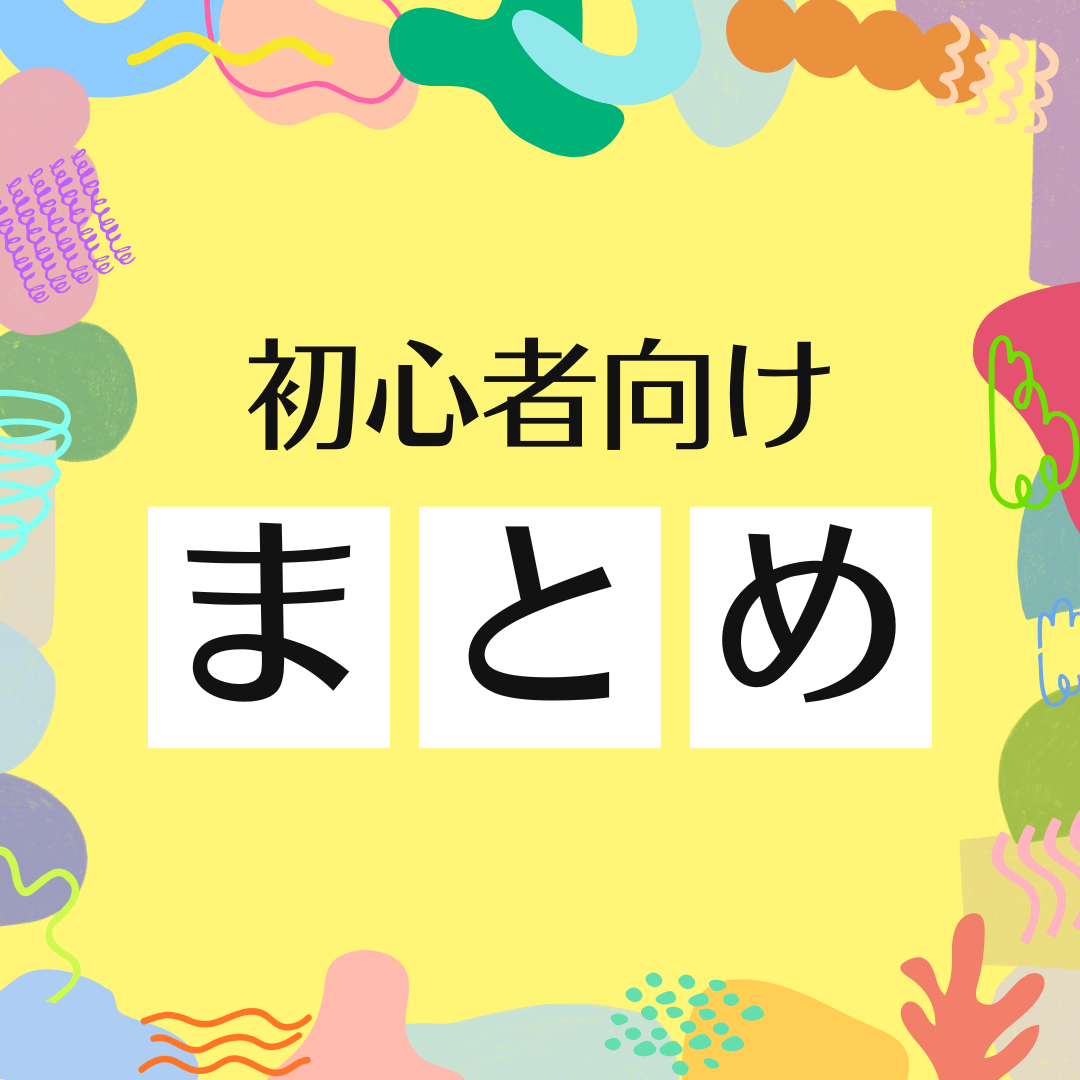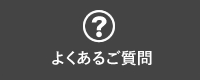2026/1/6 更新 選考対策
ケース面接とは?例題と解答パターン/対策法/体験談で完全網羅!【28卒】
- 26卒
- 27卒
- ケース面接
- ケース面接対策
- 就活
- 就職活動
- 面接対策
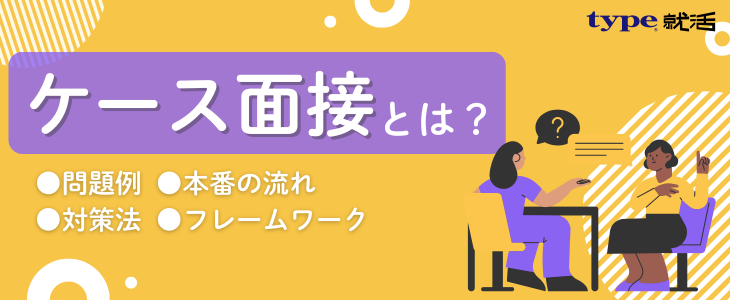
ケース面接完全網羅|目次
皆さんこんにちは、type就活です!
今回の記事では新卒採用におけるケース面接について取り上げます。
ケース面接が行われる目的、解き方、例題と解説、練習方法などケース面接に必要な全ての要素を完全網羅した記事になっております!
ぜひお役立てください。
>>>イベントの確認をする
▼インターン・選考情報はこちら
>>>インターン・選考にエントリーする
ケース面接とは?
ケース面接とは、面接官から提示されたビジネス上の課題や問題に対して、限られた時間の中で解決策を考え、それを論理的に説明する面接形式です。
単なる知識や経験を問うのではなく、問題解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力など、
コンサルタントやビジネスパーソンとして必要なスキルを総合的に評価します。
例:「近年、若者の間でコーヒーの消費量が減少しています。あるコーヒーチェーン店を経営していると仮定して、この状況を打破するための施策を提案してください。」
■ケース面接が行われている企業とは?
ケース面接はコンサルティングファーム(戦略、総合、IT)、総合商社など
一般的に入社難易度が高いと言われている企業や外資系企業で多く取り入れられています。
■なぜケース面接が行われているのか?
ケース面接は、実際の業務で直面するような状況をシミュレートすることで、
候補者が現場でどのように考え、行動するかを予測するために実施されます。
企業は、知識や経験だけでなく、問題解決能力やプレッシャーへの対応力など、ポテンシャルを重視して採用したいと考えています。
ケース面接は、そうしたポテンシャルを見極めるための有効な手段と言えるでしょう。
■新卒就活におけるケース面接の特徴
新卒におけるケース面接では、以下の点が評価されます。
問題解決能力:課題の本質を捉え、論理的な思考プロセスを経て、具体的な解決策を導き出せるか
論理的思考力:考えを整理し、筋道を立てて説明できるか。また、面接官からの質問に矛盾なく答えられるか
コミュニケーション能力:自分の考えを分かりやすく伝えられるか。また、面接官と円滑なコミュニケーションを取れるか
主体性・積極性:積極的に質問したり、追加情報を求めたりする姿勢があるか
- フェルミ推定とケース面接
よく目にする「フェルミ推定」も、ケース面接の種類の1つと言えます。
フェルミ推定とは限られた情報から、論理的思考を駆使して、未知の量を概算する手法です。
「シカゴにピアノの調律師は何人いるか?」「日本に電柱は何本あるか?」といった、一見すると答えようがないと思われるような問題に対して、手元にある情報と論理的な思考を用いて、おおよその数値を推定します。
ケース面接においては「ある企業の売上を2倍にするには?」というお題に対し、まずフェルミ推定を用いて売り上げの概算を導き、その後フェルミ推定の思考内容や結果を用いながら売上の向上策について議論をする、という方法がとられることがあります。
フェルミ推定についても記事の内容で対策可能ですので、ぜひ同時に意識しながら対策してみましょう。
ケース面接の基本的な流れ
ケース面接は一般的に以下の3つのパートに分かれます
①検討:面接官からもらったお題に対し、一人で解答を考えるフェーズ(0~10分程度)
②発表:考えた結果を面接官に共有するフェーズ(1分程度)
③議論:面接官からの質問への解答を中心に思考内容について面接官と話し合うフェーズ(10~30分程度)
- 検討と発表(10分程度):基本的な流れの例
1. 問題提示
面接官から、ある企業や業界に関する問題が提示されます。問題設定は様々ですが、市場規模の推定、新規事業の立案、収益改善など、企業が実際に直面するような課題が出題されることが多いです。
例:「近年、若者の間でコーヒーの消費量が減少しています。あるコーヒーチェーン店を経営していると仮定して、この状況を打破するための施策を提案してください。」
2. 前提情報の理解
ケース面接に回答するうえで前提となる状況のすり合わせを行います。どれくらいの前提条件が提示されるかは企業によって大きく異なり、問題文のみの場合もあればびっしりと前提が書かれたスライドを見せられる場合もあります。
ケース面接ではここの理解がとても大切で、意図的に引っ掛かりのある問題文や前提が提示される場合もあります。
質問例①:「若者」は10〜20代という想定でよいですか?
質問例②:「コーヒーチェーン店全体を経営している」という理解でよいですか?
3. 現状分析
提示された問題の前提を確認し、現状分析を行います。前提の時点で面接官との認識のずれが生じると問題に解答できていないと判断されてしまうため、自分の中で理解が曖昧な点は積極的に質問しましょう。
現状分析をチェックする手段として有用なのがフレームワークです。
3C、4P、AIDMAなどのフレームワークを適切に用いることで自分の思考の抜け漏れを排除することができます。
(フレームワークの例については後ほどの項目で解説します。)
検討すべき項目例:
①若者のコーヒー離れの原因は何か?(価格、嗜好の変化、競合の出現など)
②ターゲット層は?(年齢、性別、ライフスタイルなど)
③競合他社の状況は?(商品、価格、戦略など)
④企業の経営状況は?(売上、利益、店舗数など)
4. 課題仮説の特定
収集した情報と現状分析を元に、解決すべき課題を絞り込みます。
現状分析した中から、提示された問題の解決に繋がるかつ経営努力で操作可能な要素を絞り込み、その真の原因となっている課題を仮説ベースで1つに特定します。
明確な評価軸をもって課題を特定することが重要で、論理的思考力が問われています。
課題仮説の例:
①若者のコーヒー離れの原因として、カフェの増加による選択肢の多様化や、健康志向の高まりが考えられる。
②特に20代女性の間で、時間的制約や価格の高騰によりカフェに行く頻度そのものが減少している。
5. 解決策の提案
分析結果と仮説に基づいて、具体的な解決策を考案します。
様々な切り口から施策を検討し、実現可能性、費用対効果、リスクなどを適切に判断し、最適な解決策を提案しましょう。
解決策の例:
低糖質ドリンクや、フルーツを使ったカラフルなドリンクを開発し、若者層にアピールする。
写真映えする店内装飾や、限定グッズなどを用意し、SNSでの拡散を促す。
学生向けの割引キャンペーンや、ポイントカードを導入し、リピーター獲得を図る。
- 議論(10~30分程度):基本的な流れの例
ケース面接における最も大切なパートです。これまでのフェーズがおおよそ5分ほどで行われるのに対し、ここから15分から30分ほど時間を使って、面接官とともに自分の回答をブラッシュアップしていきます。
面接官からの質問例:
他の客層についてはどう考えているか?
競合他社が同様の施策を打ち出してきた場合はどう対応するのか?
新規メニュー開発におけるリスクは?
議論を行う際のポイント:
➢面接官とのコミュニケーションを大切にし、積極的に質問や意見交換を行う。
➢論理的な思考力と、分かりやすい説明を心がける。
➢独創的なアイデアよりも、実現可能で筋道の通った解決策を提案する。
➢落ち着いて、自信を持って面接に臨む。
常に相手をリスペクトし、自分の意見を柔軟に変化させていくことが大切です。
ケース面接の代表的な問題パターンと例題
ここからはケース問題の代表的な問題パターンを、いくつかに分類しながら紹介します。
■売上向上・利益改善- ‣ある地域密着型のスーパーマーケットの売上が低迷しています。どのように売上を向上させますか?
- ‣あるアパレルメーカーの利益率が低下しています。どのような対策を講じますか?
- ‣近年利用者が減少している遊園地の売上を増加させるには、どのような施策が考えられますか?
- ‣あるカフェの客単価を上げるには、どのような方法がありますか?
- ‣ある化粧品メーカーが海外市場に進出する際の戦略を立案してください。
- ‣シェアリングエコノミーサービスの利用者を拡大するには、どのような戦略が考えられますか?
- ‣人工知能(AI)技術を活用して、企業の成長を促進するにはどうすればよいでしょうか?
- ‣自動運転技術の普及に伴い、自動車業界はどのように変化していくと考えられますか?
- ‣都市部における渋滞を解消するにはどうしたらよいでしょうか?
- ‣高齢化社会における医療費増加問題への対策を提案してください。
- ‣満員電車に関わる諸問題を解決するための取り組みを考えてください。
- ‣教育格差を解消するために、どのような政策が有効でしょうか?
- ‣ある企業を買収する際に検討すべき項目を網羅的かつ構造的に提示してください。
- ‣ある企業の利益が低迷している原因を網羅的かつ構造的に提示してください。
- ‣あなたがタイムマシンを発明しました。どのように活用しますか?
- ‣世界中で共通の言語が使われるようになったら、どのような変化が起こるでしょうか?
- ‣地球上に宇宙人が来訪しました。どのように対応しますか?
- ‣あなたが100億円を手に入れたら、どうしますか?
形式を意識することで、自分が過去に経験したケース問題をより活かしやすくなります。
ケース面接の対策方法
ここからは、ケース面接の具体的な対策方法を解説します。
- 問題の解き方の基礎をインプット
まずはケース問題の基本的な解き方の流れをインプットしましょう。
おすすめはケース対策本です。考え方がやや古いという意見もありますが、基礎的な思考法が抑えられているためケース対策を始められたばかりの方にはおすすめです。
とくに有名な「東大生が書いた」シリーズは基本的なケース面接の解き方と簡単な例題が掲載されており、最初の一歩にぴったりです。
東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノートはこちら
- 問題を解いて慣れよう
基本的な流れをつかめたら、とにかくたくさん問題を解きましょう。
解きまくるべき理由はずばり思考の引き出しが増え、時間当たりの思考量を増やせるからです。
ケース面接に挑むにあたって、引き出しの多さは正義です。
問題のテーマとなるビジネスケースは無限にあり、それに対応するためという意味ももちろんあります。
それよりもむしろ面接官とのディスカッションに備える意味合いの方が大きいです。
自分の考えを発表したのちの面接官とのディスカッションでは多くの場合、最初の発表以外の考え方を問われることになります。例えば、
「このセグメントに着目しました」
⇒「それ以外のセグメントで考えるとしたら?」
「自社のこの強みを活かしてこの施策を行います」
⇒「これは今なぜやっていないの?デメリットがあるとすれば?」
というように、全く考えていなかったことについて面接官との会話の中でノータイムで考える必要があります。
ケース面接の評価はディスカッションの中でかなり左右されます。ですから自分の中に選択肢をたくさん持っておくことが大切なのです。
- 面接形式で実践
ケース面接では思考内容をいかに面接官に伝えるかが非常に重要です。
逆に、どれだけ素晴らしい思考ができていたとしてもそれが面接官に伝わらなければ評価されることはありません。
ここではそんな「伝達」を強化するための練習をいくつか紹介します。
ラバーダック・デバッグとは、もともとはプログラミングの世界で生まれた「自分の思考内容を確認する」ための方法です。
思考した内容を実際に誰か(何か)に向かって話してみることで、自分の話す能力を高めます。
ラバーダック・デバッグの実践方法
- ①アヒルの人形を用意します。(なんの人形でもOKです。)
- ②ケース問題に取り組み、解答を考えます。
- ③アヒルの人形に向かって、問題の内容、自分の考え、結論を説明します。
ただ人形相手に話すだけですが、以下のような効果が期待できます!
思考の整理:
声に出して説明することで、頭の中が整理され、論理の抜けや矛盾に気づくことができます。
説明力の向上:
簡潔で分かりやすい説明を心がけることで、相手に伝わる説明の練習になります。
客観性の獲得:
第三者に説明するような意識を持つことで、客観的に自分の考えを評価することができます。
壁打ちとは、学生同士で面接官役と受験者役に分かれて模擬面接を行う練習方法です。
実際の面接に近い状況を再現することで、緊張感や時間制限の中で自分の力を発揮できるよう練習することができます。
壁打ちを通して、以下の能力を鍛えることができます。
コミュニケーション能力:
面接官との質疑応答を通して、スムーズなコミュニケーション能力を養うことができます。
プレゼンテーション能力:
自分の考えを分かりやすく説明する能力を高めることができます。
対応力:
予期せぬ質問や反論に対して、冷静に対応する力を身につけることができます。
壁打ちの実践方法
- ①友人や先輩、メンターなど、協力してくれる相手を見つけます。
- ②面接官役と受験者役に分かれます。
- ③実際のケース面接を想定して、問題を解き、説明します。。
- ④壁打ち後には、良かった点、改善点などをフィードバックし合いましょう。
壁打ちを効果的に行うためのポイント
相手を意識する:
・独り言ではなく、相手に伝わるように意識して話しましょう。
フィードバックを活かす:
・相手の意見を参考に、改善点を意識して練習しましょう。
本番を想定する:
・時間制限を設けるなど、本番に近い状況で練習しましょう。
また、type就活では大手内定のインターン生による就活相談室を開催しています!
壁打ちにぜひご活用ください!
type就活インターン生による就活相談室はこちら
対策の質と量、どちらも高めていくことが大切です。 少しずつ実践に移し、実力を磨いていきましょう!
ケース面接対策:フレームワークの活用
- フレームワークの効果的な使い方とは?
ケース面接というと「フレームワークに当てはめて分析して...」というやり方を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、そのやり方は推奨しません!
なぜならフレームワークによって自分の思考の幅が狭まってしまったり、重要でない論点に時間を費やしてしまう可能性があるからです。
ではどう活用すればよいのか?
フレームワークはあくまで自分の思考に抜け漏れがないかチェックする役割で使用するのがおすすめです。
- 使えるフレームワークを紹介
3C
Customer(顧客)、Company(自社)、Competitor(競合)の3つに分けて分析することで、自社の置かれている環境を網羅的に分析できるフレームワークです。
顧客≒市場と置き換えることで、特に売上向上系のケースでは思考全体の枠組みを作るのに役立ちます。
AIDMA
AIDMA(アイドマ)は、消費者の購買フローを分析するフレームワークです。
Attention(注意)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の頭文字を取ったもので、消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでのプロセスを5つに分けて分析します。
特に現状分析では市場や顧客のある1つの状態のみに注目して分析をしてしまいがちですので、AIDMAのようなフローを分析できる手段を持っておくと役立ちます。
アンゾフの成長マトリクス
アンゾフの成長マトリクスとは、経営戦略のフレームワークの一種で、企業の成長戦略を検討する際に用いられるツールです。
事業の成長を「製品」と「市場」の2軸に分け、その2軸をさらに「既存」と「新規」に分けた4つのセクションで表します。
この4つのセクションは、「市場への浸透」「市場の開拓」「製品開発」「多角化」と言い換えられ、企業の成長戦略を検討する際に活用されます。
特に施策を考える際、マトリクスの他の窓に良い戦略がないか検討することができます。
ケース面接対策:企業別対策
多くの企業には、出題するケース問題の特性があり、その情報が共有されていたりします。
例えば、
・某戦略ファームではこのタイプの問題が出題されやすい
・この企業では標準的なケース問題が出題され、ディスカッションでは意見の柔軟性が大切
といったことです。
こういった情報は就活情報共有サイトに体験談として投稿されていたり、大きな企業であれば対策ページが作られていたりします。
また、去年同じ企業の選考を受けた先輩や、早期日程で受けた同期からも情報を得られるでしょう。
ただし、情報の確度には注意が必要です。
企業側も自社の選考が表面的に対策されることは望ましく思っていないため、毎年、毎回問題形式を大きく変えることがあります。
情報は参考程度に活用し、本質的な実力を高めることに集中するのがよいでしょう。
ケース面接完全網羅|まとめ
ケース面接対策講座、いかがでしたか?
ケース面接はトップ企業の面接における重要なフェーズです。
難易度は高いですが、対策しだいで選考通過レベルまで実力を高めることはどなたでも可能です!
またケース面接を行わないという方でも、ケース面接の練習をすることでGD対策になります。
ケース面接自体が「一人GD」のようなものであるため、お題を見た瞬間にチームでするべき議論がわかり、グイグイ引っ張ることができます。
ぜひ実力を高め続けることを意識しながら、ケース面接の練習に取り組んでみてください。
type就活限定!シークレットイベント招待・スカウトを受け取る方法
type就活のイベントに参加をすると、type就活会員限定のシークレットイベントに参加・限定スカウトが届くことも! 詳細はこちらご覧ください!
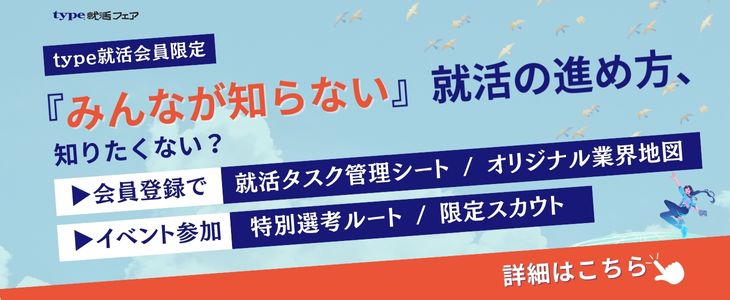
選考に進むあなたへ 就活を有利にすすめられる!おすすめイベント
スケジュール通りに進めるだけでなく、効果的に準備を行いたい場合は、就活イベントへの参加がおすすめです。
type就活では、様々なニーズにあわせたイベントが沢山開催されています。
なかには、企業研究に役立つイベントも!
早めの段階から就活イベントに参加し、有利な就職活動を始めてみましょう。
■イベント・合説の情報はこちら
 |
■インターン・本選考の情報はこちら
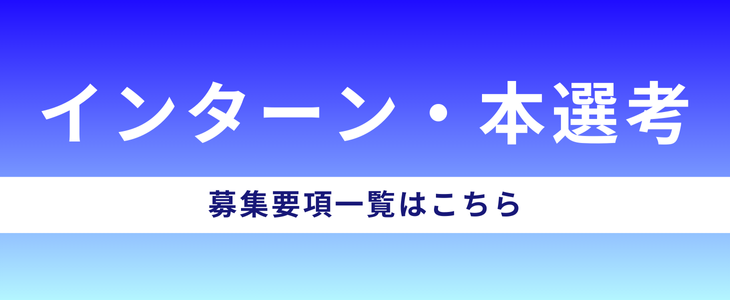 |
■就活を有利に、余裕を持って進めたい方へ!
就活はやることが多く、情報も溢れているので、その中から本当に自分に必要な情報だけを取捨選択していくことは、非常に大変だと思います。
そのため、「就活生のスケジュールに合わせたイベント情報・大手企業からのスカウト、インターン情報や選考情報」を効率よく手に入れられる、というのが理想的ではないでしょうか?
type就活では、そんな忙しい就活生のために、必要な情報を皆様にまとめてお届けしています。
就活生の皆様は、type就活に登録をするだけ!
興味のあるイベントやインターンシップ、選考情報があれば、ぜひエントリーください!就活生のスケジュールに合わせて情報を発信していますので、「もっと早く動けばよかった…」ということがなくなるでしょう。就活を少しでも有利に、余裕を持って進めたい方は、ぜひtype就活にご登録ください!
>>>新規会員登録はこちら
- 執筆者
執筆:S.I.(東北大学4年 / type就活インターン)
大学3年次よりtype就活インターンに従事。現在はゼミでの卒論執筆に苦戦中。自身の就職活動で感じたリアルな悩みや役に立つ豆知識をtype就活のコンテンツを通して皆さんにお届け。
監修:増野 杏奈(株式会社キャリアデザインセンター type就活フェア局)
外資系ホテルでの戦略立案・販売管理を経て、2024年8月に株式会社キャリアデザインセンターへ入社。「type就活」の運営メンバーとして、イベント企画や公式LINE運用、サイト改善まで幅広く担当。
ホテル業界で培った「顧客ニーズの先読み」をSEOに転用。公式LINEの反応や学生の行動データといった「一次情報」を徹底解析し、コンテンツ改善を牽引 。その結果、PV数119%・CV数165%の大幅成長を実現。
仕事の原動力は、ユーザーの心理的な満足。情報の正確さはもちろん、「失敗したくない」という不安に寄り添い、読後に「就活を頑張ろう」と前向きになれる温度感のある発信が信条 。2025年のAI検索時代において、AIには模倣できない「共感と納得」を伴うアンサーエンジン最適化(AEO)を追求中 。
公式X:https://x.com/typeshukatsu
公式Instagram:https://www.instagram.com/typeshukatsu/