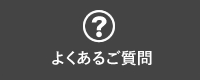-
- type就活エージェント|企業特集
- 企業紹介
- 【26卒】兼松エレクトロニクス株式会社
2025/2/19 更新 企業紹介
【26卒】兼松エレクトロニクス株式会社
業界
IT/専門商社
会社概要
・設立|1968年・資本金|90億3125万円
・売上高|906億円(2024年3月31日時点)
・本社所在地|〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10
・従業員数|単体473名、連結1,551名 (2024年3月31日時点)
・代表者|代表取締役社長 渡辺 亮
事業内容
ITインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク、ドキュメントなど)とそれに関わるサービス事業を基盤に、大企業から中堅企業のお客様の情報システムの設計・構築およびシステムコンサルティング、IT製品(システム)の販売導入、その後の運用・保守サービスまで、付加価値の高いソリューションビジネスを提供しています。長年培ってきた基盤システムのノウハウや技術力を活かしたITインフラの設計、構築を実施することで、お客様視点での最適なITソリューションを提供しているところが当社の特徴です。
柔軟性・スピードを武器に、特定のメーカー・製品・手段等にとらわれず自在にそれらを組み合わせた提案をおこない、様々なビジネスモデルや情報戦略を創り上げています。
会社の特色
~ITインフラを支えるマルチベンダー型のIT商社~◆兼松エレクトロニクス(以下 KEL)は総合商社「兼松」のグループ企業で、IT商材を専門に取り扱っている企業で、お客様視点を最重要視したITインフラサービスを、販売・設計・構築・保守・運用までワンストップで提供しています。
一般的にインフラといえば人の生活を支えるために不可欠な電気・ガス・水道・道路・鉄道などといった社会基盤のことを指しますが、企業が事業活動を進めていくために必要不可欠な会計や販売管理システムなどのITシステムの基盤となるものを「ITインフラ」といいます。
KELは、ITインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク、ドキュメントなど)とそれに関わるサービス事業を基盤に、大企業から中堅企業のお客様の情報システムの設計・構築およびシステムコンサルティング、IT製品(システム)の販売導入、その後の運用・保守サービスまで、付加価値の高いソリューションビジネスを提供しています。
お客様の大規模なITシステムが安定稼動するために必要な基盤となるハードウェアを中心としたサーバー(処理装置)やストレージ(記憶装置)、ネットワーク(通信機器)などのITシステム装置を、マルチベンダーとして特定のメーカーに縛られることなく、世界各国のメーカー製品を組み合わせることができる独立性と高い技術力を持っているのが特徴です。
~ITの知識がなくても社員の成長をバックアップする環境/ワークライフバランスが考えられた職場~
◆ITの知識がなくても安心して入社いただける、社員の成長をバックアップする環境を整えています。
KELではITに詳しくなくても入社後しっかりと教育する研修制度があります。 まず、入社後約2カ月半の研修では、ビジネスマナーからIT技術スキルなどの基礎的な知識を学んでいただき、配属後はOJT教育を通じてより専門的な知識を学ぶ事で新入社員が段階的に成長できる体制になっています。
また、資格取得奨励制度もあり、自主的に学ぶ意欲がある社員を会社全体で応援しており、この研修体系により、先輩社員は文理に関係なく幅広く活躍しています。
◆手厚い制度など、ワークライフバランスが考えられた職場です。
KELは、福利厚生や制度の整備にも目を向けています。
例えば、お休みにおいては、有給休暇、年末年始休暇、特別休暇、記念日休暇、ボランティア休暇、産休育休など様々。
また、収入においては、各種手当の他、資格取得奨励として業務に必要な資格だけでなく自己啓発に繋がる資格も対象に、資格取得者へ奨励金を支給し、他にも、独身寮・社宅、財形貯蓄、退職金、宿泊・レジャー・スポーツなどの 会員制福利厚生支援サービスへの加入、リラックス効果による生産性の向上を目的とした服装自由化など多岐に渡ります。
こうした働きやすさを意識した取り組みなどから、経済産業省の「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」にも認定されています。
募集職種:総合職(営業職/エンジニア職)※職種別採用
総合職(営業職/SE職)※ES提出の際に選択していただきます
営業職
・お客様からの質問や、「もっとこうしたい」といった課題に対して、マルチベンダーの特性を生かし、中立的な視点からIT技術やIT動向を踏まえた情報を提供します。 解決策を提案するに際は、営業が主導して解決策を導き出すプロジェクトチームを結成し、技術的な知識で営業をサポートしてくれるプリセールスや、製品情報に精通した製品担当、ときには社外のメーカー担当者も加わり、プロジェクトを進めていただきます。
SE職
・営業と同行して直接、お客様のお困りごとを聞くこともあり、技術的な視点から解決策を考え、提案内容に盛り込むためにアドバイスをします。 提案内容を実際にシステムとして使えるように
1. 要件定義、2. 基本設計、3. 詳細設計・構築、4. テスト検証、5. 導入という順でシステム構築をしていただきます。
エントリー総合職(営業職/SE職)※ES提出の際に選択していただきます
営業職
・お客様からの質問や、「もっとこうしたい」といった課題に対して、マルチベンダーの特性を生かし、中立的な視点からIT技術やIT動向を踏まえた情報を提供します。 解決策を提案するに際は、営業が主導して解決策を導き出すプロジェクトチームを結成し、技術的な知識で営業をサポートしてくれるプリセールスや、製品情報に精通した製品担当、ときには社外のメーカー担当者も加わり、プロジェクトを進めていただきます。
SE職
・営業と同行して直接、お客様のお困りごとを聞くこともあり、技術的な視点から解決策を考え、提案内容に盛り込むためにアドバイスをします。 提案内容を実際にシステムとして使えるように
1. 要件定義、2. 基本設計、3. 詳細設計・構築、4. テスト検証、5. 導入という順でシステム構築をしていただきます。